クリスマスツリーっていつ出していつ片づけたらいいの?

こんにちは!長野県松本市で小顔矯正サロンkinoeを運営しております、栗林きのえです。
クリスマスが大好きな私にとって、毎年この季節が近づいてくると、心がウキウキしてきます。
クリスマスツリーを飾る瞬間は、大人になった今でも特別な時間なんです。
けれども、「クリスマスツリーって、いつ出すのが正解なの?」
「しまうタイミングはいつ?」と、毎年悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
私も以前は「なんとなく12月に入ったら飾ろうかな」と思っていましたが、
実はクリスマスツリーを飾るタイミングには、伝統的な意味や由来があるんです。
また、クリスマスツリーに飾るオーナメント一つ一つにも、深い意味が込められています。
星や天使、ベルやリンゴ…それぞれがどんな意味を持っているのか、知ると更にクリスマスが楽しくなりますよね。
今回の記事では、2025年版のクリスマスツリー完全ガイドとして、飾るタイミングからしまうタイミング、
オーナメントの意味、そして安く飾り付ける裏ワザまで、たっぷりとお伝えしてまいります。
この記事でわかること:
- クリスマスツリーを出す最適なタイミング(2025年版)
- 伝統的な「待降節(アドベント)」とは?
- 日本独自の「クリスマスツリーの日」
- 近年のトレンド「ハロウィンから出す」裏ワザ
- しまうタイミングとNG行動
- オーナメントが持つ深い意味
- 安く飾り付ける裏ワザ
- クリスマスツリーの歴史と由来
クリスマスを心から楽しみたい方、ツリーの飾り付けを検討している方、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
きっと「今年はこのタイミングで飾ろう!」と、ワクワクしていただけるはずです。
クリスマスツリーはいつ出す?2025年版タイミング完全ガイド

クリスマスツリーを飾るタイミングには、
宗教的な伝統と、近年のライフスタイルに合わせたトレンドの二つの考え方があります。
この章では、2025年版として、それぞれのタイミングを詳しく解説してまいります。
伝統的な「待降節(アドベント)」を参考にする


クリスマスツリーを飾る最も伝統的なタイミングは、
キリスト教の「待降節(たいこうせつ/アドベント)」という期間です。
待降節とは、クリスマス(12月25日)の準備を始める期間のこと。
12月25日の4週間前の日曜日から12月24日までを指します。
この期間にクリスマスツリーを飾れば、伝統的には間違いないということですね。
2025年の待降節はいつ?
2025年の場合、11月30日に一番近い日曜日から待降節が始まります。
具体的には、2025年11月30日(日)から12月24日(水)までが待降節となります。
この期間にクリスマスツリーを飾り始めれば、伝統に則った正しいタイミングということになるんです。
私がこの待降節のことを知ったのは、実は数年前のこと。
それまでは「なんとなく12月に入ったら飾ろうかな」と思っていたのですが、待降節の意味を知ってからは、
「クリスマスの準備期間として、この時期から心を整えるんだな」と、
より深くクリスマスを楽しめるようになりました。
日本での実際の習慣
日本においても、11月下旬から12月上旬ごろにツリーを飾り始める方がほとんどです。
商業施設やショッピングモールも、この時期にクリスマスツリーを飾り始めますよね。
これは意識的に待降節に合わせているというよりも、
「11月下旬になるとクリスマスの雰囲気が出てくるから」という理由が多いようです。
けれども、結果的に伝統的な待降節の期間と重なっているというのは、面白いですよね。
サロンkinoeでも、11月下旬になるとクリスマスの飾り付けを始めます。
お客様も「もうこんな季節なんですね」と笑顔になってくださるので、
クリスマスの飾り付けには特別な力があるなと感じます。
日本独自の習慣「クリスマスツリーの日」
日本には独自の習慣として、12月7日を「クリスマスツリーの日」として飾るという考え方もあるんです。
なぜ12月7日なの?
1886年(明治19年)12月7日、輸入食品を扱うスーパーマーケット「明治屋」の創業者である磯野計が、
横浜で日本人として初めてクリスマスツリーを飾ったとされています。
この歴史的な出来事を記念して、12月7日が「クリスマスツリーの日」とされているんです。
日本のクリスマスツリーの歴史は意外と古いんですよね。
江戸時代の1860年には、プロイセン王国の公使が大きなモミの木を持ち込んでツリーを飾ったという記録もあります。
けれども、日本人が飾ったのは1886年が最初だったんですね。
12月7日に飾るメリット
12月7日に飾り始めると、クリスマス当日までちょうど良い期間ツリーを楽しめます。
「あまり早く飾ると飽きてしまうかも」と心配な方には、このタイミングがおすすめです。
また、「日本独自の記念日に合わせて飾る」というのは、なんだか特別な気持ちになりますよね。
私も今年は12月7日を意識して飾り付けをしてみようかなと思っています。
近年のトレンド「ハロウィンから出す」裏ワザ
近年、新しいトレンドとして注目されているのが、
ハロウィンが終わると同時にクリスマスツリーを出すという方法です。
ハロウィンツリーとは?
「ハロウィンツリー」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、クリスマスツリーにジャックオーランタンやおばけ、
ガーランドなどのハロウィン仕様の飾り付けをしたものです。
ハロウィン(10月31日)が終わったら、飾り付けをクリスマス仕様に変えるだけ。
これなら、10月下旬から12月下旬まで、約2ヶ月間もツリーを楽しめるんです。


ハロウィンツリーのメリット
- 長い期間ツリーを楽しめる:10月から12月まで、秋冬のインテリアとして活躍します。
- 飾り付けの手間が一度で済む:ツリー本体を出すのは一度だけ。オーナメントを変えるだけなので楽です。
- 季節感を演出できる:ハロウィンもクリスマスも楽しめて、お得感があります。
実は私も、昨年初めてハロウィンツリーに挑戦してみたんです。最初は「クリスマスツリーにハロウィンの飾り?」と半信半疑だったのですが、やってみると意外と可愛くて、サロンにいらっしゃるお客様にも好評でした。
ハロウィンが終わって、オーナメントをクリスマス仕様に変える作業も、なんだか楽しくて。「衣替え」みたいな感覚で、季節の移り変わりを感じられるのが良いなと思いました。
ハロウィンツリーの注意点
ただし、伝統を重んじる方や、「クリスマスツリーはクリスマスのためのもの」という考えの方には、少し抵抗があるかもしれません。あくまで「近年のトレンド」として楽しむものと考えると良いでしょう。
結局、いつ出すのがおすすめ?
ここまで色々なタイミングをご紹介してきましたが、結局のところ、どのタイミングが一番良いのでしょうか。
おすすめのタイミング:
- 伝統を重視するなら:11月30日(日)から(2025年の待降節開始日)
- 日本の習慣を重視するなら:12月7日(クリスマスツリーの日)
- 長く楽しみたいなら:10月下旬から(ハロウィンツリーとして)
- 一般的なタイミング:11月下旬から12月上旬
正直なところ、「これが絶対正しい!」というタイミングはありません。ご家族のスケジュールや、お部屋の状況、そして何より「飾りたい!」と思った気持ちを大切にするのが一番だと思います。
私がサロンkinoeで大切にしているのは、「お客様一人ひとりに合った提案をすること」。クリスマスツリーも同じで、ご自身やご家族が一番楽しめるタイミングで飾るのが正解だと思うんです。
あ、それから、週末など家族が揃う日に飾り付けをすると、みんなで楽しめて良い思い出になりますよ。私も子どもの頃、家族でクリスマスツリーを飾った思い出は、今でも心に残っています。
クリスマスツリーはいつしまう?NG行動も解説

クリスマスツリーを出すタイミング以上に悩むのが、「いつしまうか」ですよね。
この章では、しまうタイミングと、日本での注意点(NG行動)について詳しく解説してまいります。
伝統的な「降誕節」の終わりとは
キリスト教の伝統では、クリスマス(12月25日)から1月5日までの12日間を「降誕節(こうたんせつ)」と呼び、この期間内はクリスマスのお祝いをするのが主流です。
そして、降誕節の翌日である1月6日を「公現祭(こうげんさい)」と呼び、この日にクリスマスツリーを片付けます。
つまり、伝統的には「クリスマスツリーは1月6日までは飾っておいて良い」ということなんですね。
意外と長く飾れることに驚かれる方も多いのではないでしょうか。
私も最初にこの事実を知った時は、「え、そんなに長く飾っておいていいの?」と驚きました。
日本ではクリスマスが終わるとすぐに片付けるイメージがあったので。
日本でのおすすめの「しまうタイミング」
けれども、日本には独自の文化があります。それが「お正月」です。
なぜ日本では早めに片付けるべきなのか
日本では、大晦日(12月31日)から三が日(1月1日〜3日)にかけて、お正月のお祝いをします。
この時期に西洋のクリスマスツリーが飾られていると、お正月の雰囲気と合わないと感じる方が多いんです。
また、お正月には門松やしめ飾りといった日本の伝統的な装飾を飾りますよね。
クリスマスツリーとお正月飾りが同時に存在すると、なんだか落ち着かない空間になってしまいます。
日本でのNG行動:年越しまでツリーを飾っておく
日本の文化に合わせるなら、12月31日の大晦日や、三が日(1月1日〜3日)までクリスマスツリーを飾っておくのはNG行動とされています。
おすすめのしまうタイミング:
- 12月26日:クリスマスが終わった翌日。最も早いタイミング。
- 12月28日〜30日:年末の大掃除と一緒に片付ける。おすすめのタイミング。
- 遅くとも12月31日の午前中まで:お正月の準備が始まる前に。
私は毎年、12月27日か28日頃にクリスマスツリーを片付けています。
年末の大掃除と一緒に片付けると、「今年も一年お疲れ様」という気持ちで、
ツリーにも感謝しながら丁寧に片付けられるんです。
片付ける際の注意点
クリスマスツリーを片付ける際には、いくつか注意点があります。
1. オーナメントは丁寧に包む
ガラスのオーナメントや繊細な飾りは、来年も使えるように丁寧に包んで保管しましょう。
新聞紙やプチプチ(エアクッション)で包むと安心です。
2. ツリーの枝を整える
人工のツリーの場合、枝を畳む際に無理に押し込むと、来年広げた時に形が崩れてしまいます。
説明書に従って丁寧に畳みましょう。
3. 収納場所は湿気の少ない場所を
湿気の多い場所に保管すると、カビや劣化の原因になります。なるべく乾燥した場所に保管しましょう。
4. 小さなパーツは袋にまとめて
小さなオーナメントのフックや、LEDライトの電池など、
小さなパーツはジップロックなどの袋にまとめておくと、来年探す手間が省けます。
サロンkinoeでも、季節ごとのインテリアを定期的に変えるのですが、
「来年も使えるように丁寧に片付ける」ことを心がけています。
お気に入りのオーナメントは、毎年会える大切な友達のような存在ですからね。
生木のツリーの場合は?
最近は人工のツリーが主流ですが、本物のモミの木を使った生木のツリーを飾る方もいらっしゃいますよね。
生木のツリーの処分方法
生木の場合は、12月26日頃には片付けて、適切に処分する必要があります。
自治体によって処分方法が異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
- 粗大ゴミとして出す:多くの自治体では粗大ゴミとして回収してくれます。
- 燃えるゴミとして出す:小さく切れば、燃えるゴミとして出せる地域もあります。
- リサイクルプログラムを利用する:一部の地域では、クリスマスツリーのリサイクルプログラムがあります。
生木のツリーは本物の香りや質感が楽しめる反面、処分の手間がかかるのが難点ですね。
けれども、その分特別感があって、一度は体験してみたいなと思っています。
クリスマスツリーの歴史と由来

クリスマスツリーを飾る習慣は、どこから始まったのでしょうか。
この章では、クリスマスツリーの歴史と由来について、詳しく解説してまいります。
知れば知るほど、クリスマスツリーへの愛着が深まりますよ。
クリスマスツリーの起源
クリスマスツリーの由来については、実は諸説あるんです。
その中でも最も有力とされているのが、「北ヨーロッパのゲルマン民族の祭り」から派生したという説です。
ゲルマン民族の「ユール」
北ヨーロッパに住むゲルマン民族は、「ユール」という冬至のお祭りを行っていました。
彼らは永遠の象徴として樫の木を祭祀に使っていたんです。
けれども、キリスト教の宣教師たちがゲルマン民族の祭りを「異教」と判断し、
彼らの祭りを止めさせようと樫の木を切ってしまいます。
奇跡のモミの木
すると、切られた樫の木からすぐにモミの木が生えてきました。
この光景に驚いた宣教師たちは、モミの木の三角錐の形に感動します。
というのも、この形は神とイエス・キリスト、精霊がつながる「三位一体」を表しているとされたためです。
この出来事をきっかけに、クリスマスツリーにモミの木が使われるようになったと言われています。
私もこの話を初めて聞いた時、「切られた木から新しい木が生える」という奇跡的な出来事が、
クリスマスツリーの始まりだったことに感動しました。
自然の力強さと、それを神の奇跡として受け止めた人々の信仰心が伝わってきますよね。
日本初のクリスマスツリーは江戸時代
日本とクリスマスツリーの歴史も、意外と古いんです。
1860年:外国人が飾った最初のツリー
国内で初めてクリスマスツリーが飾られたのは、なんと江戸時代の1860年です。
プロイセン王国の公使・オイレンブルクが、大きなモミの木をプロイセン王国公館に持ち込み、
イエス・キリストの誕生を祝ったとされています。
幕末の日本に、すでにクリスマスツリーがあったなんて驚きですよね。
当時の日本人は、この異国の飾りをどんな風に見ていたのでしょうか。
1874年:日本人が初めてクリスマスを祝う
1874年を皮切りに、日本人がクリスマスを祝うようになりました。
日本人で初めてクリスマスを祝ったのは実業家の原胤昭で、
彼はキリスト教に入信したことへの感謝を表すために、クリスマスを祝うお祭りを開いたとされています。
1886年12月7日:日本人が初めてツリーを飾る
そして、日本人が初めてクリスマスツリーを飾ったのは、1886年12月7日のこと。
輸入食品を扱うスーパーマーケット「明治屋」の創業者である磯野計が、
外国人船員のために横浜で飾ったと言われています。
この日が、先ほどご紹介した「クリスマスツリーの日」の由来なんですね。
日本のクリスマスの歴史は約150年。
意外と短いようで、それでもこれだけ深く文化に根付いているというのは、
クリスマスの持つ魅力の大きさを物語っていますよね。
なぜモミの木なのか
クリスマスツリーといえば、モミの木が定番ですが、なぜモミの木なのでしょうか。
モミの木が選ばれる理由:
- 常緑樹である:冬でも緑の葉を保つモミの木は、「永遠の命」を象徴しています。
- 三角錐の形:神とイエス・キリスト、精霊の「三位一体」を表しています。
- 香りが良い:生のモミの木は、爽やかな森の香りがします。
- 丈夫で長持ち:室内に置いても比較的長持ちする樹種です。
日本では生のモミの木を手に入れるのは難しいですが、人工のツリーもモミの木を模したデザインが主流ですよね。
その背景には、こういった深い意味があったんです。
オーナメントが持つ深い意味

クリスマスツリーに飾るオーナメント一つ一つにも、実は深い意味が込められています。
この章では、代表的なオーナメントの意味を詳しく解説してまいります。
知ると、飾り付けがもっと楽しくなりますよ。
トップスター:ベツレヘムの星
クリスマスツリーの一番上に飾られる星は、「ベツレヘムの星」を表しています。
ベツレヘムとは、イエス・キリストが生まれたとされるユダヤの地名です。
聖書によると、イエスの誕生時に東の空に明るい星が現れ、
その星のおかげで三人の賢人(東方の三博士)がイエスの元へ導かれたと言われています。
この「ベツレヘムの星」が、トップスターの由来なんです。
私も子どもの頃、クリスマスツリーの一番上に星を飾るのが大好きでした。
背伸びをして、やっとの思いで星を飾る瞬間は、「これでツリーの完成!」という達成感があって、
今でも覚えています。
天使:ガブリエル
星の代わりに、天使の形をした飾りをツリーの一番上に飾る方もいらっしゃいますよね。
この天使は、ガブリエルという天使を象徴しています。
ガブリエルは、聖母マリアがイエスを体に宿したことを伝えた天使です。
国によって違う習慣
イギリスでは、ツリーの一番上に天使を飾る人も少なくありません。
星も天使も、どちらもイエスの誕生を示すものとして同じ意味を持っていますが、
国によってこうした違いがあるのも面白いですね。
日本では星が主流ですが、天使も可愛らしくて素敵です。お好みで選んでみてください。
ベル:喜びの音
ベルの飾りは、イエス・キリストの誕生を告げた音を象徴しています。
キリスト教におけるベルの音は「喜び」を表し、イエスの誕生を祝うクリスマスには必須の飾りとされています。
教会の鐘の音も、同じように喜びを告げる音なんですね。
ベルの飾りは、ゴールドやシルバーのメタリックな色が多く、ツリー全体に華やかさをプラスしてくれます。
私もベルの飾りは大好きで、複数個飾ることが多いです。
リンゴ・オーナメントボール:禁断の果実
リンゴの形をした飾りや、さまざまな色のオーナメントボールは、
アダムとイブが口にした「禁断の果実」を表現しています。
旧約聖書によると、アダムとイブはエデンの園で神から
「知恵の木の実を食べてはいけない」と言われていたにもかかわらず、蛇にそそのかされて食べてしまいます。
その果実がリンゴだったとされているんです。
なぜ禁断の果実を飾るの?
「罪」を象徴するリンゴを、なぜお祝いのツリーに飾るのか不思議ですよね。
これは、「イエス・キリストの誕生によって、人類の罪が赦された」という意味が込められているとされています。
現代では、リンゴの代わりにカラフルなオーナメントボールを飾ることが多いですが、
その由来を知ると、また違った見方ができますね。
靴下:幸運とプレゼント
靴下のオーナメントは、サンタクロースのモデルとなった聖ニコラウスに由来しています。
聖ニコラウスは、貧しい家族を救うために家に金貨を投げ入れました。
その金貨が、偶然吊るされていた靴下の中に入ったという逸話があります。
この話から、靴下の中にプレゼントを入れる習慣が始まったとされているんです。
子どもの頃、枕元に靴下を置いて「サンタさんが来ますように」と祈った記憶はありませんか?
あの習慣も、この聖ニコラウスの逸話から来ているんですね。
私もサロンkinoeのツリーに靴下を飾っていますが、
お客様のお子様が「サンタさんの靴下だ!」と喜んでくださると、こちらも嬉しくなります。
キャンディケイン:杖の形のキャンディ
キャンディケイン(キャンディケーン)とは、杖(ステッキ)を模したキャンディのことです。
赤と白のストライプ柄が特徴的ですよね。
これを飾る理由は諸説あります:
- ゲルマン民族がユールに飾る際に掛けやすい形状をしていたから
- 杖の形がイエスのことを示す「J」に似ているから
- 羊飼いの杖を表していて、イエスが「良き羊飼い」とされることから
地域によって解釈が異なるようですが、どの説も興味深いですね。
キャンディケインは見た目も可愛らしく、ツリーに掛けるだけで一気にポップな雰囲気になります。
また、実際に食べられるキャンディとして飾る方もいらっしゃいますよね。
リース:永遠の愛
輪っかの形をしたクリスマスリースは、
永遠を象徴するオーナメントで、「終わりのない神の愛」を意味するものとされています。
リースは、始まりも終わりもない円の形をしていることから、「永遠」「無限」を表しているんです。
また、ヨーロッパでは悪いものを追い払う幸運のお守りとしても信じられています。
リースは、ツリーに飾るだけでなく、玄関のドアに飾る方も多いですよね。
私もサロンの入口にクリスマスリースを飾っています。お客様を温かくお迎えする気持ちを込めて。
柊(ヒイラギ):豊穣と生命力
柊(ヒイラギ)の葉は、ギザギザとトゲのある形をしていますよね。
柊で編まれたリースは、イエスが磔にされたときに頭に乗せていた冠を表しているとされています。
トゲが、イエスの受けた苦しみを象徴しているんです。
また、柊の木は冬でも緑色の葉を茂らせているため、そんな柊に豊穣や豊作への願いをかけるという意味もあります。
柊の葉は、緑と赤の組み合わせがクリスマスカラーとして美しく、リースやガーランドによく使われています。
オーナメントの意味を知ると飾り付けが楽しい
こうしてオーナメント一つ一つの意味を知ると、飾り付けがもっと楽しくなりませんか?
私も以前は「かわいいから」「きれいだから」という理由だけで飾っていましたが、それぞれの意味を知ってからは、
「このベルは喜びを表しているんだな」「この星がイエス様を導いたんだな」と考えながら飾るようになりました。
サロンkinoeでも、お客様に「このオーナメント、実はこんな意味があるんですよ」とお話しすると、
「知らなかった!」「面白いですね」と興味を持ってくださいます。
知識があると、会話も弾みますよね。
安く飾り付ける裏ワザとコスパ重視の選び方
クリスマスツリーは、本体だけでなく飾り付けにもお金がかかりますよね。
けれども、工夫次第で安くておしゃれに仕上げることができるんです。
この章では、コスパ重視の飾り付け裏ワザをご紹介いたします。
裏ワザ1:天然素材を活用する
松ぼっくりや木の実、ドライフルーツなど、
安く手に入る天然素材をグルーガンで飾り付けるだけで、温もりのある北欧風のツリーが完成します。
天然素材のメリット:
- 安い:公園で拾った松ぼっくりなら無料!
- ナチュラルな雰囲気:自然素材ならではの温かみがあります。
- 環境に優しい:プラスチックのオーナメントより環境負荷が少ない。
- 子どもと一緒に楽しめる:公園で松ぼっくりを拾う時間も楽しい思い出に。
私も以前、近所の公園で松ぼっくりを拾って、金色のスプレーで塗ってツリーに飾ったことがあります。
思いのほか高級感が出て、お客様からも「素敵ですね!」と褒めていただきました。
天然素材アレンジのアイデア:
- 松ぼっくりに金や銀のスプレーを吹きかける
- ドライフルーツ(オレンジやレモンの輪切り)を吊るす
- シナモンスティックをリボンで結んで飾る
- どんぐりに紐を通して飾る
天然素材の良いところは、香りも楽しめることです。シナモンスティックやドライフルーツは、
ほのかに良い香りがして、視覚だけでなく嗅覚でもクリスマスを楽しめますよ。
裏ワザ2:100円ショップやプチプラアイテムを活用
最近の100円ショップは、クリスマスオーナメントの品揃えが本当に充実していますよね。
100円ショップ活用のコツ:
- 大量に必要なものは100円ショップで:
小さなボールオーナメントなど、たくさん必要なものは100円ショップで揃えましょう。 - 高見えするアイテムを部分的に:
LEDライトや大きめのオーナメントなど、目立つアイテムは少し良いものを選ぶと、全体が引き締まります。 - 色を統一する:100円ショップのアイテムでも、色を統一すれば高級感が出ます。
私も毎年、100円ショップでオーナメントを少しずつ買い足しています。
「今年はゴールド系で統一しよう」「来年はシルバーとホワイトで」と、テーマカラーを決めて選ぶのが楽しいんです。
裏ワザ3:手作りオーナメントに挑戦
手作りオーナメントは、世界に一つだけのオリジナルツリーを作れる上に、材料費も抑えられます。
簡単に作れる手作りオーナメント:
- フェルトのオーナメント:フェルトを星やツリー、雪だるまの形に切って、簡単に縫い合わせるだけ。
- 折り紙の星:折り紙で立体的な星を作って吊るす。
- 写真オーナメント:家族の写真を小さな額に入れて飾る。思い出も一緒に飾れます。
- 塩生地のオーナメント:小麦粉と塩と水で作った生地を型抜きして乾燥させ、色を塗る。
手作りオーナメントの良いところは、お子様と一緒に作る時間も楽しめること。
私も姪っ子と一緒にフェルトのオーナメントを作ったことがありますが、
「これは私が作ったやつ!」と嬉しそうに指差す姿が可愛らしかったです。
裏ワザ4:LEDライトで華やかさアップ
ツリーを一気に華やかにするのがLEDライトです。
最近のLEDライトは価格も手頃になり、1,000円〜2,000円程度で購入できます。
ライトを巻きつけるだけで、ツリーが何倍も美しく見えるので、コスパ最強のアイテムと言えるでしょう。
LEDライトの選び方:
- 電球色:温かみのある優しい光。ナチュラル系のツリーにおすすめ。
- 白色:クールで洗練された雰囲気。モダンなインテリアに合います。
- カラフル:ポップで楽しい雰囲気。お子様がいるご家庭におすすめ。
私はサロンのツリーには電球色のLEDライトを使っています。
温かみのある光が、リラックスした雰囲気を作ってくれるんです。
裏ワザ5:去年のオーナメントを再利用&アレンジ
毎年新しいオーナメントを買わなくても、
去年のオーナメントを再利用&アレンジすることで、新鮮な気持ちで飾り付けができます。
再利用アレンジのアイデア:
- 色あせたオーナメントをスプレーで塗り直す
- リボンを新しいものに変える
- 配置を変えて新鮮な印象に
- 去年とテーマカラーを変える(例:去年は赤×金、今年は白×銀)
「もったいない精神」は、日本の素晴らしい文化だと思います。
大切に使い続けることで、オーナメントにも愛着が湧きますよね。
おすすめのクリスマスツリーの選び方
ツリー本体を選ぶ際も、コスパを意識したいですよね。
サイズの選び方:
- 120cm:一人暮らしや省スペースにおすすめ。
- 150cm:ファミリー向け。存在感がありつつ、圧迫感は少ない。
- 180cm以上:広いリビングや、豪華な雰囲気を出したい方に。
タイプの選び方:
- ヌードツリー:オーナメントは別売り。自分好みにカスタマイズできる。
- オーナメントセット:届いたらすぐに飾れる。初心者におすすめ。
- LEDライト付き:ライトが最初から付いているので楽。
- ハーフツリー:壁際に置ける省スペースタイプ。
私は、最初は「オーナメントセット」から始めて、
翌年以降に少しずつ自分好みのオーナメントを買い足していくのがおすすめだと思います。
一度に全部揃えようとすると、予算もかかりますし、迷ってしまいますからね。
クリスマスツリーを楽しむためのコツと注意点
クリスマスツリーを最大限に楽しむためのコツと、気をつけたい注意点をご紹介します。
飾り付けを家族やお友達と楽しむ
クリスマスツリーの飾り付けは、家族やお友達と一緒に楽しむのが一番です。
一人で黙々と飾るのも良いですが、みんなでワイワイと飾り付けをする時間は、それ自体が素敵な思い出になります。
お子様がいるご家庭なら、お子様に好きなオーナメントを選んでもらったり、
飾る場所を決めてもらったりするのも楽しいですよね。
私もサロンのツリーを飾る時は、スタッフと一緒に「これはここがいいかな?」
「いや、もう少し上の方が良くない?」と話しながら飾ります。その時間が、なんだか楽しくて。
飾る場所に注意
クリスマスツリーを飾る場所も大切です。
避けた方が良い場所:
- 暖房器具の近く:乾燥して火災の危険性があります。特に生木の場合は注意。
- 通路:人がぶつかってツリーが倒れる危険があります。
- 直射日光が当たる場所:オーナメントが色あせたり、LEDライトが劣化する原因に。
おすすめの場所:
- リビングの隅:家族みんなが見られる場所。
- 玄関:お客様を迎える場所に飾ると、クリスマスムードが高まります。
- 窓際:外から見ても楽しめます。ただし、直射日光には注意。
私は、サロンの受付カウンターの横にツリーを飾っています。
お客様がいらっしゃった時に、最初に目に入る場所なので、「わぁ、素敵!」と喜んでいただけるんです。
安全対策も忘れずに
特に小さなお子様やペットがいるご家庭では、安全対策が重要です。
安全対策のポイント:
- ツリーをしっかり固定する:倒れないように土台をしっかりと。
- 割れやすいオーナメントは高い位置に:小さなお子様の手が届かない位置に飾りましょう。
- LEDライトの配線に注意:コードに引っかかって転ばないように。
- ペットがかじらないように:オーナメントやライトをペットがかじらないよう注意。
あ、それから、LEDライトは長時間つけっぱなしにしても比較的安全ですが、
外出時や就寝時は消しておくと安心ですね。
写真をたくさん撮る
せっかく素敵に飾り付けたツリーですから、写真をたくさん撮って記録に残しましょう。
毎年同じ場所で写真を撮ると、
「去年と比べてこんなに成長したんだな」とお子様の成長を実感できますし、家族の大切な思い出になります。
私も毎年、サロンのツリーの写真を撮ってSNSに投稿しています。
お客様から「今年のツリーも素敵ですね!」とコメントをいただくと、嬉しくなります。
よくある質問
クリスマスツリーについて、よくある質問をQ&A形式でまとめました。
Q1. クリスマスツリーは毎年出さないといけませんか?
いいえ、必ずしも毎年出す必要はありません。
ご家庭の事情や気分によって、「今年は忙しいから出さない」という選択も全く問題ありません。
クリスマスツリーは、楽しむためのものですから、無理をする必要はないんです。
私も、引っ越しをした年は荷物の整理で忙しくて、ツリーを出さなかったことがあります。
けれども、「来年はまた飾ろう!」と思えば良いんです。
Q2. 小さな子供がいても安全に飾れますか?
工夫次第で安全に飾れます。
- 割れやすいガラスのオーナメントは避けて、プラスチック製のものを選ぶ
- 小さなパーツのオーナメントは高い位置に飾る
- ツリーをしっかり固定する
- ペットゲートやベビーゲートでツリーの周りを囲む(可能であれば)
お子様と一緒に飾り付けを楽しむことで、「クリスマスツリーは大切なもの」という意識も育まれますよ。
Q3. 賃貸でもクリスマスツリーは飾れますか?
はい、問題なく飾れます。
賃貸住宅でも、床を傷つけないように気をつければ大丈夫です。
ツリーの土台の下にマットやカーペットを敷くと、床への負担も軽減できます。
また、大きなツリーを置くスペースがない場合は、卓上サイズの小さなツリーもおすすめです。
玄関やテーブルの上に飾るだけでも、十分クリスマス気分を味わえますよ。
Q4. ツリーのサイズはどう選べば良いですか?
お部屋の天井の高さと、設置スペースを考慮して選びましょう。
目安:
- 天井高2.4m:150cm以下のツリー
- 天井高2.7m:180cm以下のツリー
- 天井高3.0m以上:180cm以上のツリーも可
また、ツリーは横にも広がるので、周囲にも十分なスペースを確保できるサイズを選びましょう。
私の経験では、「思ったより大きかった!」となるよりも、
「少し小さめかな」と思うくらいのサイズの方が、圧迫感がなくて良いように思います。
Q5. 生木のツリーと人工のツリー、どちらがおすすめですか?
それぞれにメリットがあります。
生木のツリー:
- メリット:本物の香り、質感、特別感
- デメリット:手入れが大変、処分が必要、毎年購入費用がかかる
人工のツリー:
- メリット:繰り返し使える、手入れが楽、長期的にはコスパが良い
- デメリット:香りや質感は本物に劣る
個人的には、「初めてのクリスマスツリー」なら人工のツリーから始めるのがおすすめです。
慣れてきて、「本物のモミの木も体験してみたい!」と思ったら、生木に挑戦してみるのも良いでしょう。
Q6. オーナメントは何個くらい用意すれば良いですか?
ツリーのサイズによりますが、目安としては以下の通りです。
- 120cmツリー:30〜50個
- 150cmツリー:50〜80個
- 180cmツリー:80〜120個
ただし、これはあくまで目安。
「ぎっしり飾りたい」という方はもっと多く、「シンプルに」という方は少なめでも良いでしょう。
私は「少し隙間があるくらいが、かえって上品に見える」という考えなので、少なめに飾ることが多いです。
Q7. LEDライトは何メートル必要ですか?
ツリーのサイズによって必要な長さが変わります。
- 120cmツリー:3〜5m
- 150cmツリー:5〜10m
- 180cmツリー:10〜15m
「多めに用意して、余った分は他の飾りに使う」という考え方もありますね。
窓際や玄関にもライトを飾ると、クリスマスムードが一層高まります。
Q8. ツリーの保管方法を教えてください
来年も美しく使うために、適切に保管しましょう。
保管のポイント:
- オーナメントは丁寧に包んで、専用の箱に入れる
- ツリー本体は説明書に従って畳み、収納袋に入れる
- 湿気の少ない場所に保管する
- 重いものを上に乗せない
私は、オーナメント用に卵パック(紙製)を使っています。
小さなオーナメントを一つずつ入れられて、クッション性もあるので便利ですよ。
Q9. クリスマスが終わったら、すぐに片付けないといけませんか?
日本の習慣を考えると、12月31日までには片付けることをおすすめします。
けれども、「年が明けても少し飾っておきたい」という場合は、ご自身の判断で大丈夫です。
特に決まりはありませんからね。
ただし、お正月の飾りとの兼ね合いを考えると、やはり年内に片付ける方がすっきりするかと思います。
Q10. クリスマスツリーを飾ると電気代が心配です
LEDライトは消費電力が少ないので、それほど心配する必要はありません。
例えば、100球のLEDライトを1日8時間、1ヶ月間点灯させても、電気代は100円〜200円程度です。
クリスマスの楽しみとして考えれば、許容範囲ではないでしょうか。
気になる方は、タイマー機能付きのLEDライトを使うと、消し忘れも防げて節電にもなりますよ。
まとめ:2025年のクリスマスを素敵に彩ろう
ここまで、クリスマスツリーの飾るタイミングからしまうタイミング、
オーナメントの意味、安く飾り付ける裏ワザまで、たっぷりとお伝えしてまいりました。
最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。
押さえておきたい重要ポイント
クリスマスツリーを出すタイミング:
- 伝統的には:11月30日(日)から(2025年の待降節)
- 日本独自の習慣:12月7日(クリスマスツリーの日)
- 近年のトレンド:10月下旬から(ハロウィンツリーとして)
- 一般的には:11月下旬〜12月上旬
クリスマスツリーをしまうタイミング:
- 伝統的には:1月6日(公現祭)
- 日本では:12月26日〜30日(遅くとも12月31日午前中まで)
- NG行動:年越しや三が日までツリーを飾っておくのは避ける
オーナメントの意味:
- トップスター:ベツレヘムの星
- 天使:ガブリエル
- ベル:喜びの音
- オーナメントボール:禁断の果実
- 靴下:幸運とプレゼント
- リース:永遠の愛
- 柊:豊穣と生命力
安く飾り付ける裏ワザ:
- 天然素材(松ぼっくり、ドライフルーツ)を活用
- 100円ショップやプチプラアイテムを上手に使う
- 手作りオーナメントに挑戦
- LEDライトで華やかさアップ
- 去年のオーナメントを再利用&アレンジ
サロンkinoeからのメッセージ
今回、クリスマスツリーについて詳しく調べてみて、
改めて「クリスマスツリーって、こんなに深い意味があったんだ!」と驚きました。
単なる飾りではなく、一つ一つのオーナメントに込められた意味、
そして飾るタイミングやしまうタイミングにも、伝統や文化が反映されているんですね。
サロンkinoeでは、お客様のココロとカラダの健康を大切にしています。
美しさを追求するだけでなく、心が満たされること、幸せを感じることも、とても大切だと考えているんです。
クリスマスツリーを飾って、きらめく光を見て、「きれいだな」「幸せだな」と感じる時間は、まさに心の栄養。
日常の忙しさを忘れて、クリスマスの特別な雰囲気の中で過ごす時間は、私たちの心を豊かにしてくれます。
最後に
2025年のクリスマスは、ぜひこの記事を参考に、ご自身のタイミングで、
ご自身らしいクリスマスツリーを飾ってみてください。
伝統を重んじるも良し、近年のトレンドを取り入れるも良し、安く工夫して飾るも良し。
大切なのは、「クリスマスを楽しむ」という気持ちです。
オーナメント一つ一つの意味を知って飾れば、
いつもとは違った特別な気持ちでクリスマスツリーを眺められるはずです。
「この星はベツレヘムの星なんだ」「このベルは喜びを表しているんだ」と思いながら飾ると、
クリスマスがもっと深く、豊かなものになりますよね。
そして、飾り付けの時間も、家族やお友達と一緒に楽しんでください。
ワイワイと話しながら飾る時間は、それ自体が素敵な思い出になります。
クリスマスツリーが、皆さんのお家を温かく、そして幸せな空間に変えてくれますように。
サロンkinoeも、今年のクリスマスツリーをどう飾ろうか、今からワクワクしています。
お客様にも「今年のツリーも素敵ですね!」と言っていただけるよう、心を込めて飾り付けをしたいと思います。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!
皆さん、ぜひこの冬は素敵なクリスマスツリーを飾って、特別なクリスマスをお過ごしくださいね。
メリークリスマス!🎄✨
・【珈琲館】ピングーコラボ夏の福袋「2025サマーバッグ」完全ガイド
・【サマー福袋】ビッグボーイ夏の福袋完全ガイド
・【2025年速報】イオンで見つけた!ハーゲンダッツ福袋が保冷バッグ付きで激アツ!
・【タリーズ】夏の福袋2025完全ガイド│6/18発売!
-

【ポケモン福袋2026】ピカピカボックス追加抽選は1/16まで!中身ネタバレと倍率、当選確率を上げる裏ワザを解説
-

【カルディ福袋2026】キャンセル分再販はいつ?中身ネタバレと店頭・オンライン購入のコツ!口コミや倍率も解説
-

【GYDA(ジェイダ)福袋2026】中身ネタバレ!トートバッグやミニバッグなど福袋のお得度や予約いつまで?再販や口コミも徹底解説
-

【パペットスンスン福袋2026】中身ネタバレ!楽天限定8,980円の内容はぬいぐるみや食品?予約いつ?再販や口コミも徹底解説
-

【ゴディバ福袋2026】中身ネタバレ!100周年記念3種の違いや予約いつ?クーポンやアウトレット、口コミ・コスパも徹底解説
-

【ユニクロ初売り2026】いつまで?1月8日までの期間やチラシの中身、湯呑みノベルティ・口コミを徹底解説
-

【マンウィズ福袋2026】中身ネタバレ!マンハッタンポーテージコラボの予約はいつまで?再販や口コミ、お届け時期も徹底解説
-

【にゅ/サンガッチョ福袋2026】中身ネタバレ!靴2足セットの予約いつまで?再販や口コミ、サイズ感も徹底解説
-

【ONIGIRI福袋2026】中身ネタバレ!ボアコート入り豪華5点セットは予約いつ?再販や口コミ、コスパも徹底解説
-

【コムサイズム福袋2026】中身ネタバレ!コートやジレ入りレディース3種のコスパは?予約いつ?再販や口コミも徹底解説
-

【マリークワント福袋2026】中身ネタバレ!コスメDセット等の内容は?予約いつ?再販や口コミ、コスパも徹底解説
-

【ナンガ福袋2026】中身ネタバレ!バケツの中身は?予約いつ?再販や口コミ、コスパを徹底解説



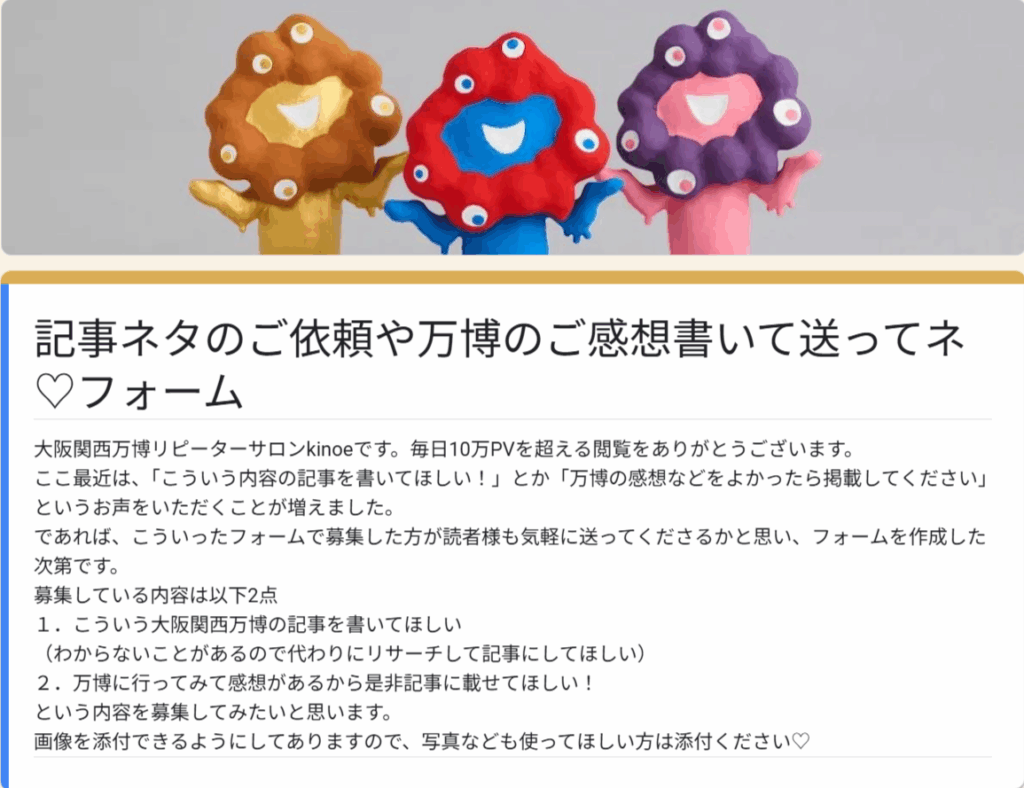




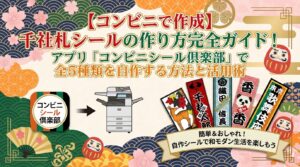
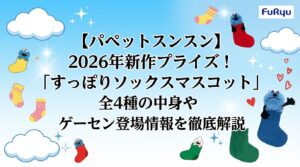

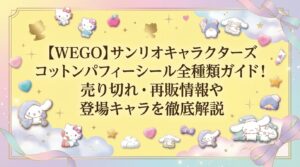

コメント