呼ばれないと行けない神社10選:神域からの招待状、その神秘と注意点


「呼ばれないと行けない神社」という言葉を聞いたことがありますか? これは、特定の神社とご縁が深い人、あるいはその神社に参拝するべきタイミングが来た人だけが、何らかの形で招かれるようにして訪れることができる、という神秘的な考え方です。
今回は、そんな「呼ばれないと行けない」と噂される神社を10社厳選し、それぞれの神社の概要、特徴、そして参拝時の注意点などを詳しくご紹介します。
もし、あなたがこれらの神社に呼ばれたのなら、それはきっと特別な意味があるはず。神様からのメッセージを受け取りに、ぜひ足を運んでみてください。
※注意:
「呼ばれないと行けない」という概念は、あくまでスピリチュアルな考え方であり、科学的な根拠はありません。しかし、多くの人々が、特定の神社との不思議な縁を感じていることも事実です。
ここでは、そのような体験談や言い伝えが多く存在する神社を、厳選してご紹介します。
「呼ばれる」とは?
「呼ばれる」体験は人それぞれですが、以下のような形で現れることが多いようです。
- 夢で見る: 夢の中に、特定の神社が繰り返し出てくる。
- 偶然の出会い: たまたま立ち寄った場所が、その神社の近くだった。
- 人から勧められる: 知人や友人から、特定の神社を強く勧められる。
- シンクロニシティ: その神社の名前や関連する情報を、何度も目にしたり聞いたりする。
- 直感: 理由もなく、その神社に行きたいという強い衝動に駆られる。
1. 戸隠神社(長野県)


- 住所: 長野県長野市戸隠
- 御祭神:
- 奥社:天手力雄命(あめのたぢからおのみこと)
- 中社:天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)
- 宝光社:天表春命(あめのうわはるのみこと)
- 九頭龍社:九頭龍大神(くずりゅうのおおかみ)
- 火之御子社:天鈿女命(あめのうずめのみこと)
- 特徴:
- 五社(奥社、中社、宝光社、九頭龍社、火之御子社)からなる、広大な神社。
- 古くから山岳信仰の霊場として知られ、強力なパワースポットとしても有名。
- 奥社参道には、樹齢400年を超える杉並木があり、神秘的な雰囲気が漂う。
- 注意点:
- 奥社への参道は、約2kmの道のりで、一部険しい場所もあるため、歩きやすい靴で参拝すること。
- 冬季(11月下旬~4月下旬)は、奥社への参道が閉鎖される場合があるため、事前に確認すること。
- 自然豊かな場所なので、熊などの野生動物に注意すること。
戸隠神社(長野県):なぜ「呼ばれないと行けない」のか?その神秘と魅力に迫る
長野県の霊峰・戸隠山の麓に鎮座する戸隠神社。奥社・中社・宝光社・九頭龍社・火之御子社の五社からなり、古くから修験道の聖地として、また近年ではパワースポットとして、多くの人々を惹きつけています。しかし、この戸隠神社には「呼ばれないと行けない」という、不思議な言い伝えがあるのをご存知でしょうか?今回は、その言い伝えの真偽と、戸隠神社の持つ特別な魅力、そして周辺のおすすめスポットまで、余すところなくご紹介します。
なぜ「呼ばれないと行けない神社」と言われているのか?:神域の結界と、試される信仰心
戸隠神社が「呼ばれないと行けない」と言われる理由は、いくつかの説があります。それらは、戸隠神社が持つ独特の歴史、地理的な特徴、そして、そこに宿る神々の力と深く結びついているようです。単なる噂や迷信ではなく、実際に訪れた人々が体験した、不思議なエピソードも数多く存在します。
- 強力な神域の結界説: 戸隠神社は、古来より神聖な場所として、強い結界が張られていると言われています。この結界は、不浄なものや、参拝にふさわしくない人を阻むとされ、心身が清浄で、神様とのご縁がある人だけが、招き入れられると考えられています。
- 厳しい修行の地説: 戸隠神社は、かつて修験道の修行場であり、厳しい自然環境の中にありました。そのため、容易に訪れることができず、修行を積んだ者や、神様に呼ばれた者だけが辿り着ける場所だった、という歴史的背景があります。
- 九頭龍大神の存在説: 戸隠神社には、九頭龍大神という、非常に強い力を持つ龍神が祀られています。この龍神は、人を選ぶとされ、ご縁のある人には、様々なサインを送って呼び寄せると言われています。
- 神様からの試練説: 戸隠神社へたどり着く途中に起こるトラブルは
神様からの試練であり、乗り越えたものだけが辿り着くことを許されるという考え方。
「呼ばれる」体験談の例:
- 何度も計画を立てるが、その度に悪天候や交通機関の乱れなど、何らかの理由で、戸隠神社行きが中止になる。
- 戸隠神社に行こうとすると、体調を崩したり、急用ができたりする。
- 逆に、予定していなかったのに、急に戸隠神社に行くことになる。
- 戸隠神社に関する情報(夢、人からの話、シンクロニシティなど)が、頻繁に目や耳に入ってくるようになる。
- 道に迷って通常のルートではない道を通って辿り着いた。
科学的根拠はないが…:
これらの体験談には、もちろん科学的な根拠はありません。しかし、偶然や気のせいでは片付けられない、不思議な体験をした人が多いのも事実です。
「呼ばれないと行けない」という言葉は、戸隠神社が持つ神秘性、そして、参拝者と神様との間の、目に見えない繋がりを象徴しているのかもしれません。
戸隠神社 おすすめスポット:五社巡りで、大地のエネルギーを全身に浴びる
戸隠神社は、奥社、中社、宝光社、九頭龍社、火之御子社の五社からなります。それぞれ異なる御祭神を祀り、異なるご利益があるとされています。五社全てを巡ることで、より強いご利益をいただけると言われていますので、ぜひ時間をかけて、ゆっくりと参拝しましょう。ここでは、それぞれの社の特徴と、おすすめの巡り方をご紹介します。
- 宝光社(ほうこうしゃ):
- 御祭神: 天表春命(あめのうわはるのみこと)…中社の御祭神・天八意思兼命の御子神
- ご利益: 開拓学問技芸の神、安産の神、女性や子供の守り神
- 特徴: 五社の中で最も低い場所に位置し、270段余りの石段を登った先に社殿があります。
- 石段に注意:体力に自信がない方は注意が必要です。
- 火之御子社(ひのみこしゃ):
- 御祭神: 天鈿女命(あめのうずめのみこと)
- ご利益: 舞楽芸能の神、縁結びの神、火防の神
- 特徴: 唯一、御朱印やお守りがない、静寂に包まれた神秘的な神社です。
- 御神木 樹齢500年を超える杉の巨木。
- 中社(ちゅうしゃ):
- 御祭神: 天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)
- ご利益: 学業成就、商売繁盛、開運、厄除、家内安全
- 特徴: 五社の中心的な存在。境内には、樹齢700年を超えるご神木、樹齢800年を超える三本杉があります。
- 社務所があり御朱印や御守りを頂くことが可能。
- 奥社(おくしゃ):
- 御祭神: 天手力雄命(あめのたぢからおのみこと)
- ご利益: 開運、心願成就、五穀豊穣、スポーツ必勝
- 特徴: 戸隠神社の本社。参道入口から約2km、徒歩40分ほどかかります。特に、参道中ほどにある「随神門」から奥は、樹齢400年を超える杉並木が続き、神聖な雰囲気が漂います。
- 九頭龍社(くずりゅうしゃ):
- 御祭神: 九頭龍大神(くずりゅうのおおかみ)
- ご利益: 水の神、雨乞いの神、虫歯の神、縁結びの神
- 特徴: 奥社に隣接して鎮座しています。戸隠山の地主神であり、古くから信仰を集めています。
おすすめの巡り方:
- 体力に自信がある方は、宝光社から奥社まで、五社全てを徒歩で巡るのがおすすめです(所要時間:約4〜5時間)。
- 体力に自信がない方や、時間がない方は、バスやタクシーを利用することも可能です。
- 季節や天候に合わせて、無理のない計画を立てましょう。
- 御朱印集めをしている場合は、五社全てで御朱印をいただくことも可能です。
戸隠神社 近隣の観光地や名所:大自然と、歴史文化が織りなす、魅力的なエリア
戸隠神社周辺には、美しい自然、歴史的な建造物、そして、美味しい蕎麦など、魅力的な観光スポットがたくさんあります。ここでは、戸隠神社と合わせて訪れたい、おすすめの場所をご紹介します。
- 鏡池: 戸隠連峰を映し出す、美しい池。特に紅葉の時期は絶景です。
- 戸隠森林植物園: 様々な植物や野鳥を観察できる、自然豊かな植物園。
- 戸隠流忍法資料館: 戸隠流忍法に関する資料を展示している資料館。忍者体験もできます。
- チビッ子忍者村: 忍者体験ができるテーマパーク。
- 戸隠そば: 戸隠神社周辺には、美味しい蕎麦屋がたくさんあります。ぜひ、本場の戸隠そばを味わってみてください。
戸隠神社は、「呼ばれないと行けない」という神秘的な言い伝えがありますが、それは、この場所が持つ特別な力、そして、訪れる人々との間に生まれる、目に見えない繋がりを象徴しているのかもしれません。
ぜひ、あなた自身の心で、戸隠神社の神秘と魅力を感じてみてください。
戸隠神社へ毎年8月8日に参拝に行っていますが、やはり5社巡りがおすすめです。
とくに奥社の参道にある門を超えると別世界が広がります。
5社それぞれ離れており、駐車場も奥社以外は台数が限られているので、
宝光社(ほうこうしゃ)と火之御子社(ひのみこしゃ)を見てから車で移動し、中社、
そしてさらに車で移動し、奥社と九頭竜神社へと向かうとスムーズです。
五社巡りのあとは戸隠名物のお蕎麦を食べていくのが通ですよ。
2. 伊勢神宮(三重県)


- 住所: 三重県伊勢市宇治館町
- 御祭神:
- 内宮(皇大神宮):天照大御神(あまてらすおおみかみ)
- 外宮(豊受大神宮):豊受大御神(とようけのおおみかみ)
- 特徴:
- 日本最高峰の神社であり、全国の神社の中心的存在。
- 内宮と外宮があり、それぞれ異なる神様を祀っている。
- 広大な敷地内には、荘厳な社殿や、美しい自然が広がる。
- 20年に一度、社殿を建て替える「式年遷宮」が行われる。
- 注意点:
- 内宮と外宮は、それぞれ別の場所にあり、距離があるため、時間に余裕を持って参拝すること。
- 参拝の際は、服装に気を配り、露出の多い服装は避けること。
- 写真撮影が禁止されている場所があるため、注意すること。
伊勢神宮(三重県):なぜ「呼ばれないと行けない」のか? 日本人の心のふるさと、その深淵なる魅力
伊勢神宮は、三重県伊勢市に鎮座する、日本最高峰の神社です。
皇室の御祖先である天照大御神を祀る内宮(皇大神宮)と、
衣食住の守り神である豊受大御神を祀る外宮(豊受大神宮)を中心に、125の宮社から成り立っています。
20年に一度、社殿を建て替える「式年遷宮」の伝統を守り続け、常に清浄な空間を保っています。
「お伊勢さん」として親しまれ、年間を通じて多くの参拝者が訪れますが、
この伊勢神宮にも「呼ばれないと行けない」という言葉を耳にすることがあります。
それは一体なぜなのでしょうか?
なぜ「呼ばれないと行けない神社」と言われているのか?:日本人の精神性と、神宮の格式
伊勢神宮が「呼ばれないと行けない」と言われる背景には、いくつかの理由が考えられます。
それは、伊勢神宮が持つ特別な格式、そして、日本人の精神性に深く根ざした信仰の形と関係しているようです。
単なる観光地ではなく、魂の浄化、そして新たな始まりを求める人々にとって、
伊勢神宮は特別な意味を持つ場所なのです。
- 日本最高峰の格式:
伊勢神宮は、全国の神社の中でも別格の存在であり、
皇室の御祖先を祀ることから、最も尊い神社とされています。
その格式の高さから、誰でも気軽に訪れるべき場所ではない、という考え方が生まれたのかもしれません。 - 神宮とのご縁:
伊勢神宮に「呼ばれる」という感覚は、人それぞれ異なりますが、
何らかの形で伊勢神宮とのご縁を感じたり、内なる声に導かれたりする、という体験をする人が多いようです。 - 浄化の力:
伊勢神宮には、強力な浄化の力があると言われています。
心身の穢れを祓い、清らかな状態でないと、神宮の神域に入ることができない、という考え方もあります。 - 「おかげさま」の精神:
伊勢神宮への参拝は、「おかげ参り」とも呼ばれ、日々の感謝の気持ちを神様に伝えるために行われてきました。
単なる個人的なお願い事をするのではなく、感謝の気持ちを持って参拝することが大切だ、
という教えが、「呼ばれないと行けない」という言葉に込められているのかもしれません。 - 人生の節目:
進学、就職、結婚など、人生の大きな節目に呼ばれるように伊勢神宮を訪れる人も多いようです。
「呼ばれる」体験談の例:
- 伊勢神宮のことを、様々な場面で、何度も目にしたり、聞いたりするようになる。
- 急に伊勢神宮に行きたいという強い衝動に駆られる。
- 夢の中に、伊勢神宮や、伊勢神宮に関係するものが現れる。
- 伊勢神宮に行く予定はなかったのに、なぜか伊勢にたどり着いてしまう。
伊勢神宮 おすすめスポット:内宮・外宮、そして別宮… それぞれの魅力を体感する
伊勢神宮は、内宮(皇大神宮)と外宮(豊受大神宮)を中心に、125の宮社から構成されています。
それぞれの宮には、異なる神様が祀られており、異なるご利益があるとされています。
ここでは、特におすすめのスポットを厳選し、その魅力と、参拝のポイントをご紹介します。
- 外宮(豊受大神宮):
- 御祭神: 豊受大御神(とようけのおおみかみ)…衣食住、産業の守り神
- 特徴: 参道は、木々に囲まれ、静かで落ち着いた雰囲気。
- おすすめスポット:
- 正宮: 豊受大御神が祀られている、外宮の中心となる社殿。
- 多賀宮(たかのみや): 豊受大御神の荒御魂(あらみたま)を祀る別宮。
- 土宮(つちのみや): 外宮の地主神である大土御祖神(おおつちみおやのかみ)を祀る別宮。
- 風宮(かぜのみや): 風の神である級長津彦命(しなつひこのみこと)と級長戸辺命(しなとべのみこと)を祀る別宮。
- 内宮(皇大神宮):
- 御祭神: 天照大御神(あまてらすおおみかみ)…皇室の御祖先、日本人の総氏神
- 特徴: 五十鈴川の清流に沿って参道を進み、宇治橋を渡ると、神聖な空気が漂います。
- おすすめスポット:
- 正宮: 天照大御神が祀られている、内宮の中心となる社殿。
- 荒祭宮(あらまつりのみや): 天照大御神の荒御魂を祀る別宮。
- 風日祈宮(かざひのみのみや): 風の神である級長津彦命と級長戸辺命を祀る別宮。
- 五十鈴川: 心身を清めるための、清らかな川。
- 別宮:
- 月讀宮(つきよみのみや): 月讀尊(つきよみのみこと)を祀る別宮。
- 倭姫宮(やまとひめのみや): 倭姫命(やまとひめのみこと)を祀る別宮。
参拝のポイント:
- 外宮から内宮へ: 古くからの習わしでは、外宮を参拝してから、内宮を参拝するのが正式な順序とされています。
- 服装: 神様の前ですので、清潔感のある服装を心がけましょう。
- 参拝作法: 二見興玉神社で禊を済ませ、手水舎で手と口を清めてから参拝しましょう。
伊勢神宮 近隣の観光地や名所:伊勢志摩の魅力を、五感で味わう


伊勢神宮周辺には、美しい自然、歴史的な建造物、
そして美味しいグルメなど、魅力的な観光スポットがたくさんあります。
ここでは、伊勢神宮と合わせて訪れたい、おすすめの場所をご紹介します。
伊勢志摩の豊かな恵みを、五感で味わい尽くしましょう。
- おかげ横丁: 江戸時代の街並みを再現した、風情ある通り。伊勢名物の赤福餅や、伊勢うどんなどを味わえます。
- おはらい町: 伊勢神宮(内宮)の門前町。お土産屋さんや飲食店が立ち並び、賑わっています。
- 二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ): 夫婦岩で有名な神社。伊勢神宮参拝前に、ここで禊を行うのが古くからの習わしです。
- 猿田彦神社(さるたひこじんじゃ): 道開きの神様として知られる猿田彦大神を祀る神社。
- 鳥羽水族館: 多種多様な海の生き物たちと出会える、人気の水族館。
- ミキモト真珠島: 真珠養殖の歴史を学べる、真珠のテーマパーク。
- 伊勢志摩国立公園: リアス式海岸の美しい景色が楽しめる、自然豊かな国立公園。
伊勢神宮は、単なる観光地ではなく、日本人の心のふるさと、そして、魂の浄化と再生を促す、特別な場所です。「呼ばれないと行けない」という言葉は、神宮とのご縁、そして、参拝にふさわしい心の状態を表しているのかもしれません。
ぜひ、あなた自身の心で、伊勢神宮の神秘と魅力を感じてみてください。
3. 出雲大社(島根県)

- 住所: 島根県出雲市大社町杵築東
- 御祭神: 大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)
- 特徴:
- 縁結びの神様として有名で、全国から多くの参拝者が訪れる。
- 旧暦10月には、全国の神々が出雲大社に集まる「神在月(かみありづき)」という神事が行われる。
- 本殿は、日本最古の神社建築様式である大社造りで、国宝に指定されている。
- 巨大なしめ縄が特徴的。
- 注意点:
- 参拝の際は、二礼四拍手一礼の作法で行うこと。
- 縁結びのお守りは、種類が豊富なので、迷ってしまうかも。
- 周辺には、出雲そばやぜんざいなど、美味しいグルメがたくさんあるので、ぜひ味わってみて。
出雲大社(島根県):なぜ「呼ばれないと行けない」のか? 縁結びの聖地、その深淵を探る
出雲大社は、島根県出雲市に鎮座し、
縁結びの神様として名高い大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)を祀る神社です。
「縁結び」と聞くと、恋愛成就をイメージするかもしれませんが、
出雲大社でいう「縁」とは、男女の仲だけでなく、仕事、友人、家族、
そして、あらゆるものとの良いご縁を結ぶことを意味します。
全国から多くの参拝者が訪れる、人気の神社ですが、この出雲大社にも「呼ばれないと行けない」という言葉を耳にすることがあります。それは一体なぜなのでしょうか?
なぜ「呼ばれないと行けない神社」と言われているのか?:神在月、神議り、そして大国主大神の導き
出雲大社が「呼ばれないと行けない」と言われる背景には、いくつかの理由が考えられます。
それは、出雲大社が持つ特別な神事、大国主大神の神徳、そして、人智を超えた神秘的な力と関係しているようです。
出雲大社は、神々が集う場所であり、神と人との縁を繋ぐ場所。
そこには、選ばれた者だけが辿り着ける、特別な世界があるのかもしれません。
- 神在月(かみありづき)の存在:
旧暦10月、全国の八百万の神々が出雲大社に集まり、
人々の縁結びについて会議(神議り/かむはかり)をすると伝えられています。
この神事の期間中は、特に神様の力が強まり、ご縁のある人を招き入れると考えられています。 - 大国主大神の神徳:
大国主大神は、縁結びの神様として有名ですが、
その他にも、国土開拓、農業、商業、医療など、様々なご利益をもたらす神様として信仰されています。
その幅広いご神徳ゆえに、縁のある人、必要としている人を、自ら招き入れると考えられています。 - 出雲という土地の力:
出雲は、古くから神話の舞台として知られ、神秘的な力を持つ土地とされてきました。
出雲大社は、その中でも特に強いパワースポットであり、
神様に呼ばれた人だけが、その力を受け取ることができる、と考えられています。 - 神様との相性
全ての人が同じ神社からご利益をいただけたり、歓迎されたりするわけではないという考え方。
相性の良い神社、そうでない神社があることも「呼ばれる」「呼ばれない」に関係しているかも。
「呼ばれる」体験談の例:
- 何度も出雲大社に行こうと計画するが、その度に何らかの理由で、行くことができなくなる。
- 逆に、予定していなかったのに、急に出雲大社に行くことになる。
- 出雲大社に関する情報(夢、人からの話、シンクロニシティなど)が、頻繁に目や耳に入ってくるようになる。
- 出雲大社を訪れた後、人生が良い方向に進み始める。
出雲大社 おすすめスポット:神話の世界を体感し、縁結びのパワーをいただく
出雲大社は、広大な敷地内に、数多くの見どころがあります。
ここでは、特におすすめのスポットを厳選し、その魅力と、参拝のポイントをご紹介します。
神話の世界に触れ、縁結びのパワーをいただき、心豊かな時間を過ごしましょう。
- 勢溜(せいだまり)の大鳥居: 出雲大社の正面入り口。ここから神域が始まります。
- 下り参道:全国的にも珍しい下り参道。参拝者の邪気を祓うともいわれています。
- 松の参道の鳥居 古代の出雲大社は現在とは異なり、すぐそこまで海が迫っていたため、船で参拝する際に通ったとされています。
- 拝殿: 大国主大神に参拝する場所。出雲大社独特の「二礼四拍手一礼」の作法で参拝しましょう。
- 本殿: 大国主大神が祀られている、出雲大社の中心となる社殿。通常は中に入ることはできませんが、外から参拝することができます。
- 神楽殿: 巨大なしめ縄が特徴的な建物。結婚式などの神事が行われます。
- 素鵞社(そがのやしろ): 大国主大神の親神である素戔嗚尊(すさのおのみこと)を祀る社。本殿の裏手にあり、強力なパワースポットとして知られています。
- 神祜殿(しんこでん): 大国主大神の御分霊を祀っている場所。
- 彰古館:さまざまな資料を収蔵した施設
- 銅鳥居: 青銅でできた鳥居。
- ムスビの御神像: 大国主大神と幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)の像は縁結びの御神像として親しまれています。
- 御慈愛の御神像: 大国主大神と因幡の白兎の像。
- 十九社(じゅうくしゃ): 神在月に全国から集まった神々が滞在する社。
- 因幡の白兎像: 出雲神話に登場する因幡の白兎の像。大国主大神との出会いを描いた場面が再現されています。
参拝のポイント:
- 「二礼四拍手一礼」の作法: 出雲大社では、通常の「二礼二拍手一礼」ではなく、「二礼四拍手一礼」の作法で参拝します。
- 御朱印: 出雲大社では、オリジナルの御朱印帳や、様々な種類の御朱印をいただくことができます。
出雲大社 近隣の観光地や名所:神話と自然、そして美味しいグルメを満喫する
出雲大社周辺には、神話ゆかりの地、美しい自然、そして、出雲ならではのグルメを楽しめるスポットがたくさんあります。ここでは、出雲大社と合わせて訪れたい、おすすめの場所をご紹介します。
- 稲佐の浜(いなさのはま): 国譲り神話の舞台となった浜。旧暦10月10日に、全国の神々をお迎えする「神迎神事」が行われます。
- 出雲日御碕神社(いずもひのみさきじんじゃ): 素戔嗚尊と天照大御神を祀る、朱塗りの社殿が美しい神社。
- 日御碕灯台: 石造りの灯台としては東洋一の高さを誇る、白亜の灯台。
- 島根県立古代出雲歴史博物館: 出雲の歴史や文化に関する資料を展示している博物館。
- 出雲そば: 出雲地方の名物。割子そばや釜揚げそばなど、様々な食べ方があります。
- ぜんざい: 出雲はぜんざい発祥の地とされています。
出雲大社は、単なる縁結びの神社ではなく、日本の神話と歴史、そして文化が息づく、特別な場所です。
「呼ばれないと行けない」という言葉は、出雲大社が持つ神秘性、
そして、訪れる人々との間に生まれる、目に見えない繋がりを象徴しているのかもしれません。
ぜひ、あなた自身の心で、出雲大社のパワーを感じ、素敵なご縁を結んでください。
4. 厳島神社(広島県)


- 住所: 広島県廿日市市宮島町
- 御祭神:
- 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)
- 田心姫命(たごりひめのみこと)
- 湍津姫命(たぎつひめのみこと)
- 特徴:
- 海上に浮かぶ大鳥居が有名で、日本三景の一つにも数えられている。
- 社殿は、平安時代の寝殿造りの様式を今に伝える、貴重な建築物。
- 潮の満ち引きによって、景色が大きく変わるのも魅力。
- 注意点:
- 宮島へは、フェリーで渡る必要がある。
- 潮の満ち引きを事前に確認し、大鳥居が海に浮かぶ姿を見たい場合は、満潮時刻に合わせて訪れること。
- 野生の鹿が多数生息しているので、餌を与えたり、近づきすぎたりしないように注意。
厳島神社(広島県):なぜ「呼ばれないと行けない」のか? 海に浮かぶ神秘の宮、その真実に迫る
世界遺産にも登録されている厳島神社は、広島県廿日市市の宮島に鎮座し、海に浮かぶ朱塗りの大鳥居が象徴的な、日本を代表する神社の一つです。その美しさから、国内外から多くの観光客が訪れますが、この厳島神社にも「呼ばれないと行けない」という、不思議な言い伝えがあるのをご存知でしょうか?今回は、その言い伝えの真相と、厳島神社の持つ神秘的な魅力、そして、周辺のおすすめスポットまで、詳しくご紹介します。
なぜ「呼ばれないと行けない神社」と言われているのか?:平清盛との関係、そして特別な神域
厳島神社が「呼ばれないと行けない」と言われる背景には、いくつかの理由が考えられます。それは、厳島神社の歴史、地理的な特徴、そして、そこに祀られている神々の力と深く関係しているようです。単なる観光地ではなく、魂の浄化、そして人生の転機を求める人々にとって、厳島神社は特別な意味を持つ場所なのです。
- 平清盛との深い関わり: 厳島神社は、平安時代末期に平清盛が厚く信仰し、現在の海上に立つ社殿群を造営したことで知られています。平家一門の繁栄を支えた神社として、特別な力を持つと考えられています。
- 特別な立地: 厳島神社は、潮の満ち引きによって、その姿を大きく変えます。満潮時には海に浮かぶように見え、干潮時には大鳥居まで歩いて行くことができます。この自然現象が、神秘的な雰囲気を醸し出し、「呼ばれないと、その姿を見ることができない」というイメージに繋がっているのかもしれません。
- 強力な浄化の力: 厳島神社には、強力な浄化の力があると言われています。心身の穢れを祓い、清らかな状態でないと、神域に入ることができない、という考え方もあります。
- 神様の相性 神社には相性があり、歓迎されない場合もあると考える人もいるようです。
- 潮の満ち引き: 潮の満ち引きによって、その姿を大きく変える厳島神社。満潮時には海に浮かぶように見え、干潮時には大鳥居まで歩いて行くことができます。この自然現象が、神秘的な雰囲気を醸し出し、「呼ばれないと、その姿を見ることができない」というイメージに繋がっているのかもしれません。
「呼ばれる」体験談の例:
- 何度も厳島神社に行こうと計画するが、その度に悪天候や交通機関の乱れなど、何らかの理由で、行くことができなくなる。
- 逆に、予定していなかったのに、急に厳島神社に行くことになる。
- 厳島神社に関する情報(夢、人からの話、シンクロニシティなど)が、頻繁に目や耳に入ってくるようになる。
- 厳島神社を訪れた後、人生が良い方向に進み始める。
- 満ち潮でスムーズに参拝できたが、その直後に急な天候悪化があった。
厳島神社 おすすめスポット:海と空と朱色のコントラスト、世界遺産の絶景を体感する
厳島神社は、その美しい景観と、歴史的な建造物が調和した、世界に誇る文化遺産です。ここでは、特におすすめのスポットを厳選し、その魅力と、参拝のポイントをご紹介します。海と空と朱色のコントラストが生み出す絶景を、心ゆくまで堪能しましょう。
- 大鳥居: 厳島神社のシンボル。海上に立つ朱塗りの大鳥居は、高さ約16m、主柱は樹齢500~600年のクスノキの自然木で作られています。
- 干潮時には、大鳥居まで歩いて行くことができます。
- 満潮時には、海に浮かぶ大鳥居の姿を見ることができます。
- 2019年から始まった大規模改修工事が2022年12月に完了
- 社殿: 平安時代の寝殿造りの様式を今に伝える、国宝・重要文化財の建造物群。
- 本社本殿: 市杵島姫命、田心姫命、湍津姫命の三女神を祀る。
- 拝殿: 参拝者が祈りを捧げる場所。
- 祓殿(はらえでん): 参拝者を祓い清める場所。
- 高舞台(たかぶたい): 舞楽などが奉納される舞台。
- 廻廊(かいろう): 社殿を結ぶ、朱塗りの美しい回廊。
- 能舞台: 国の重要文化財に指定。国内で唯一の海に浮かぶ能舞台として知られる。
- 平舞台: 社殿の前方に広がる、広い板張りの舞台。
- 五重塔 豊国神社(千畳閣)に隣接している、鮮やかな朱塗りの五重塔。
- 豊国神社(千畳閣): 厳島神社の隣にある、豊臣秀吉が建立を命じた未完の大経堂。
参拝のポイント:
- 潮の満ち引きを確認する: 潮の満ち引きによって、厳島神社の姿は大きく変わります。事前に潮見表を確認し、満潮時と干潮時の両方の景色を楽しむのがおすすめです。
- 服装: 神様の前ですので、清潔感のある服装を心がけましょう。
- 写真撮影: 境内での写真撮影は可能ですが、神様や社殿を直接撮影するのは失礼にあたる場合があるので、注意しましょう。
厳島神社 近隣の観光地や名所:宮島の魅力を、余すところなく楽しむ
厳島神社がある宮島には、豊かな自然、歴史的な建造物、そして、美味しいグルメなど、魅力的な観光スポットがたくさんあります。ここでは、厳島神社と合わせて訪れたい、おすすめの場所をご紹介します。宮島の魅力を、余すところなく満喫しましょう。
- 宮島ロープウエー: 弥山(みせん)山頂まで行くことができるロープウェー。山頂からは、瀬戸内海の絶景を一望できます。
- 弥山(みせん): 宮島の最高峰。山頂には、弘法大師(空海)が開いたとされる弥山本堂や、数々の奇岩・巨石があります。
- 紅葉谷公園: 秋には紅葉が美しい、散策にぴったりの公園。
- 宮島水族館(みやじマリン): スナメリなど、瀬戸内海に生息する生き物を中心に展示している水族館。
- 大聖院: 真言宗御室派(総本山仁和寺)の大本山。
- 表参道商店街: 宮島名物のもみじ饅頭や、牡蠣料理など、様々なお店が軒を連ねる商店街。
- 町屋通り: カフェや雑貨店などが集まる、風情ある街並みが残る通り。
厳島神社は、単なる観光地ではなく、日本の歴史と文化、そして自然が調和した、特別な場所です。「呼ばれないと行けない」という言葉は、厳島神社が持つ神秘性、そして、訪れる人々との間に生まれる、目に見えない繋がりを象徴しているのかもしれません。
ぜひ、あなた自身の心で、厳島神社のパワーを感じ、特別な体験をしてください。
5. 高千穂神社(宮崎県)
- 住所: 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井
- 御祭神:
- 高千穂皇神(たかちほすめがみ)
- 十社大明神(じっしゃだいみょうじん)
- 特徴:
- 天孫降臨の地として知られ、神話の世界を体感できる場所。
- 境内には、樹齢800年を超える秩父杉や、夫婦杉など、見どころがたくさん。
- 毎晩行われる「高千穂神楽」は、国の重要無形民俗文化財に指定されている。
- 注意点:
- 高千穂峡は、神社の近くにある、美しい渓谷。ボートに乗って、景色を楽しむのもおすすめ。
- 周辺には、天岩戸神社や天安河原など、神話にまつわるスポットが多数あるので、合わせて訪れるのも良いでしょう。
高千穂神社(宮崎県):なぜ「呼ばれないと行けない」のか? 天孫降臨の聖地、その神秘に触れる
宮崎県高千穂町に鎮座する高千穂神社は、神々が降り立った地として知られる、高千穂郷八十八社の総社です。約1900年前に創建されたと伝えられ、豊かな自然に囲まれた境内には、神秘的な空気が漂います。近年、パワースポットとしても人気を集め、多くの参拝者が訪れますが、この高千穂神社にも「呼ばれないと行けない」という言葉を耳にすることがあります。その理由は何なのでしょうか?
なぜ「呼ばれないと行けない神社」と言われているのか?:神話の世界と繋がる、特別な場所
高千穂神社が「呼ばれないと行けない」と言われる背景には、この地が持つ特別な歴史、神話との深い繋がり、そして、そこに宿る神々の力が関係していると考えられます。高千穂は、天孫降臨の地として知られ、日本神話の中でも重要な場所。神話の世界と現実世界が交差する、特別な場所だからこそ、「呼ばれる」という神秘的な体験をする人がいるのかもしれません。
- 天孫降臨の地: 高千穂は、天照大神(あまてらすおおみかみ)の孫である瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が、地上に降り立った場所(天孫降臨)として知られています。そのため、高千穂神社は、神話の世界と繋がる、特別な場所として信仰されてきました。
- 高千穂郷八十八社の総社: 高千穂神社は、高千穂郷に点在する八十八社の神社の総社であり、強い力を持つ神社として崇敬されています。その強い力ゆえに、神様とのご縁や、参拝の準備が整った人だけが、招き入れられると考えられているのかもしれません。
- 神楽の里: 高千穂神社では、毎晩「高千穂神楽」が奉納されています。神楽は、神々をもてなすための舞であり、神聖な儀式。神楽を通じて、神様との繋がりを深めることができる場所だからこそ、「呼ばれる」という特別な体験が生まれるのかもしれません。
- 自然豊かな場所: 高千穂神社は、高千穂峡をはじめとする、豊かな自然に囲まれています。その美しい自然が、神聖な雰囲気を醸し出し、「呼ばれないと、その姿を見ることができない」というイメージに繋がっているのかもしれません。
- 試される信仰心 神社までの道のりや、天候などで、「本当に参拝するに値する人物か」神様に試されていると感じる人がいるようです。
「呼ばれる」体験談の例:
- 何度も高千穂神社に行こうと計画するが、その度に何らかの理由で、行くことができなくなる。
- 逆に、予定していなかったのに、急に高千穂神社に行くことになる。
- 高千穂神社に関する情報(夢、人からの話、シンクロニシティなど)が、頻繁に目や耳に入ってくるようになる。
- 高千穂神社を訪れた後、人生が良い方向に進み始める。
高千穂神社 おすすめスポット:神話の世界を体感し、大地のエネルギーを感じる
高千穂神社は、境内全体がパワースポットと言えるでしょう。ここでは、特におすすめのスポットを厳選し、その魅力と、参拝のポイントをご紹介します。神話の世界を体感し、大地のエネルギーを感じ、心豊かな時間を過ごしましょう。
- 本殿: 高千穂皇神(たかちほすめがみ)と十社大明神(じっしゃだいみょうじん)を祀る、厳かな雰囲気の本殿。日々の感謝を伝え、心静かに祈りを捧げましょう。
- 拝殿: 参拝者が祈りを捧げる場所。神楽殿としても使われ、毎晩20時から21時に「高千穂神楽」が奉納されます(有料)。
- 夫婦杉(めおとすぎ): 根本が一つになっている二本の杉の木。縁結び、夫婦円満のご利益があるとされています。
- 夫婦杉の周りを、大切な人と手をつないで3回廻ると、幸せになれるという言い伝えがあります。
- 秩父杉(ちちぶすぎ): 樹齢800年を超える御神木。その力強い姿は、見る者を圧倒します。
- 鎮石(しずめいし): 触れると、心身の乱れや悩みが鎮まると言われる石。
参拝のポイント:
- 服装: 神様の前ですので、清潔感のある服装を心がけましょう。
- 高千穂神楽: 時間がある方は、ぜひ高千穂神楽を鑑賞してみてください。神話の世界を体感できる、貴重な体験となるでしょう。
高千穂神社 近隣の観光地や名所:神話と自然、そして美味しいグルメを満喫する
高千穂神社周辺には、神話ゆかりの地、美しい自然、そして、高千穂ならではのグルメを楽しめるスポットがたくさんあります。ここでは、高千穂神社と合わせて訪れたい、おすすめの場所をご紹介します。神話と自然、そして美味しいグルメを満喫し、思い出に残る旅にしましょう。
- 高千穂峡: 国の名勝・天然記念物に指定されている、美しい渓谷。ボートに乗って、景色を楽しむのがおすすめです。
- 天岩戸神社(あまのいわとじんじゃ): 天照大神が隠れた天岩戸をご神体とする神社。
- 天安河原(あまのやすかわら): 天照大神が天岩戸に隠れた際、八百万の神々が集まって相談したとされる場所。
- くしふる神社: 瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)が降臨した際に最初に居を構えた場所と言い伝えられ、境内には様々な巨石・奇岩が存在。
- 荒立神社(あらたてじんじゃ): 猿田彦命(サルタヒコノミコト)と天鈿女命(アメノウズメノミコト)を祀る神社。
- 高千穂牛: 高千穂の豊かな自然の中で育った、ブランド牛。ぜひ、味わってみてください。
高千穂神社は、単なる観光地ではなく、日本の神話と歴史、そして自然が息づく、特別な場所です。「呼ばれないと行けない」という言葉は、高千穂神社が持つ神秘性、そして、訪れる人々との間に生まれる、目に見えない繋がりを象徴しているのかもしれません。
ぜひ、あなた自身の心で、高千穂神社のパワーを感じ、神話の世界を体感してください。
6. 幣立神宮(熊本県)
- 住所: 熊本県上益城郡山都町大野
- 御祭神:
- 神漏岐命(かむろぎのみこと)
- 神漏美命(かむろみのみこと)
- 大宇宙大和神(おおとのちおおかみ)
- 天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)
- 天照大御神(あまてらすおおみかみ)
- 特徴:
- 「高天原神話発祥の地」「神話の源流」とされ、「人類のルーツ」「地球上で最も古い神社」と語られることもある、特別な神社。
- 強力なパワースポットとして知られ、世界中から多くの人々が訪れる。
- 樹齢1万5千年ともいわれるヒノキの巨木「五百枝杉(いおえすぎ)」がある。
- 注意点:
- 神聖な場所なので、参拝の際は、服装や言動に気を配ること。
- 周辺には、宿泊施設が少ないため、事前に予約しておくこと。
幣立神宮(熊本県):なぜ「呼ばれないと行けない」のか? 世界の聖地、その深遠なる神秘に迫る
熊本県上益城郡山都町に鎮座する幣立神宮は、「高天原神話発祥の地」「神話の源流」「地球上で最も古い神社」など、様々な言葉で語り継がれる、特別な神社です。近年、パワースポットとしても注目を集め、世界中から多くの人々が訪れますが、この幣立神宮にも「呼ばれないと行けない」という、不思議な言い伝えがあるのをご存知でしょうか?今回は、その言い伝えの真相と、幣立神宮の持つ神秘的な魅力、そして、周辺のおすすめスポットまで、詳しくご紹介します。
なぜ「呼ばれないと行けない神社」と言われているのか?:地球のへそ、人類発祥の地、そして宇宙との繋がり
幣立神宮が「呼ばれないと行けない」と言われる背景には、この神社が持つ特別な由来、地理的な特徴、そして、そこに宿る神々の力が関係していると考えられます。幣立神宮は、単なる神社ではなく、地球、人類、そして宇宙との繋がりを感じられる、特別な場所なのです。その神秘的な力ゆえに、訪れるべきタイミング、準備が整った人だけが、招き入れられるのかもしれません。
- 高天原神話発祥の地: 幣立神宮は、日本神話における神々が住む高天原(たかまがはら)の神々が、初めて地上に降臨された場所である、という伝承があります。
- 地球のへそ(ヘソ): 幣立神宮は、「地球のへそ」とも呼ばれ、地球の中心、生命の源、そして、宇宙と繋がる場所であると考えられています。
- 人類発祥の地: 幣立神宮には、人類発祥の地であるという伝承もあります。
- 強力なパワースポット: 幣立神宮は、世界でも有数のパワースポットとして知られ、強いエネルギーを持つ場所とされています。その強いエネルギーゆえに、心身の準備が整っていない人は、訪れることができない、あるいは、訪れても何も感じることができない、と言われています。
- 神域との相性: その土地や神社との相性などもあり、相性が合わない場合は辿り着くことすら難しいと考える人もいるようです。
「呼ばれる」体験談の例:
- 何度も幣立神宮に行こうと計画するが、その度に何らかの理由で、行くことができなくなる。
- 逆に、予定していなかったのに、急に幣立神宮に行くことになる。
- 幣立神宮に関する情報(夢、人からの話、シンクロニシティなど)が、頻繁に目や耳に入ってくるようになる。
- 幣立神宮を訪れた後、人生が良い方向に進み始める、人生の転機が訪れる。
幣立神宮 おすすめスポット:太古の記憶が息づく、神秘の空間
幣立神宮は、境内全体が、太古の記憶が息づく、神秘的な空間です。ここでは、特におすすめのスポットを厳選し、その魅力と、参拝のポイントをご紹介します。神聖な空気を感じ、大地のエネルギーをチャージし、心豊かな時間を過ごしましょう。
- 幣立神宮(本殿):
- 御祭神: 神漏岐命(かむろぎのみこと)、神漏美命(かむろみのみこと)、大宇宙大和神(おおとのちおおかみ)、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、天照大御神(あまてらすおおみかみ)
- 特徴: 本殿は、厳かな雰囲気。心静かに参拝し、日々の感謝を伝え、祈りを捧げましょう。
- 東御手洗(ひがしみてらし):
- 特徴: 古代の祭祀場跡であり、清らかな水が湧き出る、幣立神宮の中でも特に神聖な場所。
- 水神が祀られている: 禊の場でもあったと言い伝えられています。
- 五百枝杉(いおえすぎ):
- 特徴: 樹齢1万5千年ともいわれるヒノキの巨木。幣立神宮の御神木であり、強いパワーを感じられる場所として人気です。
- 触れることはできませんが、その存在感、大地のエネルギーを感じてみましょう。
- 幣立神宮の森:
- 特徴: 境内には、豊かな自然が広がり、森林浴を楽しむことができます。
- 巨木が多く存在。
参拝のポイント:
- 服装: 神様の前ですので、清潔感のある服装を心がけましょう。
- 礼儀作法: 参拝の際は、二礼二拍手一礼の作法で行いましょう。
- 静寂を保つ: 他の参拝者や自然の音を尊重し、静かに参拝を。
- 撮影について: 境内は基本的に撮影可能ですが、神聖な場所のため節度をもって行いましょう。
幣立神宮 近隣の観光地や名所:神話と自然、そして歴史を感じる旅
幣立神宮周辺には、神話ゆかりの地、美しい自然、そして、歴史的な建造物など、魅力的な観光スポットがたくさんあります。ここでは、幣立神宮と合わせて訪れたい、おすすめの場所をご紹介します。神話と自然、そして歴史を感じる、充実した旅を楽しみましょう。
- 通潤橋(つうじゅんきょう): 江戸時代に造られた、日本最大級の石造りアーチ水路橋。国の重要文化財に指定されています。
- 五ヶ瀬ハイランドスキー場: 九州で最も標高が高い場所にあるスキー場。冬にはスキーやスノーボードを楽しめます。
- 高千穂峡: 熊本県と宮崎県の県境近く、高千穂町にある峡谷。ボートからの眺めは圧巻です。(高千穂神社も合わせて訪れたい)
- 白川水源: 環境庁の「名水百選」に選ばれている、美しい水源。
幣立神宮は、単なる観光地ではなく、日本の神話、歴史、そして自然が凝縮された、特別な場所です。「呼ばれないと行けない」という言葉は、幣立神宮が持つ神秘性、そして、訪れる人々との間に生まれる、目に見えない繋がりを象徴しているのかもしれません。
ぜひ、あなた自身の心で、幣立神宮のパワーを感じ、神秘の世界を体感してみてください。
7. 石上神宮(奈良県)
- 住所: 奈良県天理市布留町
- 御祭神:
- 布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)
- 布留御魂大神(ふるのみたまのおおかみ)
- 布都斯魂大神(ふつしみたまのおおかみ)
- 特徴:
- 日本最古の神社の一つであり、武の神様として信仰を集めている。
- 国宝の「七支刀(ななつさやのたち)」が伝わることで有名。
- 境内には、鶏が放し飼いにされており、神の使いとされている。
- 注意点:
- 境内は、自然豊かな場所なので、虫除け対策をしておくこと。
- 鶏を追いかけたり、触ったりしないように注意。
石上神宮(奈良県):なぜ「呼ばれないと行けない」のか? 日本最古の神社、その神威と謎に迫る
石上神宮(いそのかみじんぐう)は、奈良県天理市に鎮座し、日本最古の神社の一つとして知られています。
物部氏の総氏神であり、古来より武の神様、そして健康長寿の神様として信仰を集めてきました。
神話の時代から続く神秘的な雰囲気、そして国宝の七支刀をはじめとする数々の宝物…。
この特別な神社にも、「呼ばれないと行けない」という言い伝えがあります。今回はその謎と魅力についてご紹介していきます。
なぜ「呼ばれないと行けない神社」と言われているのか?:神話の時代から続く、厳格な神域
石上神宮が「呼ばれないと行けない」と言われる背景には、この神社が持つ特別な歴史、強力な神威、そして、そこに祀られている神々との深いつながりが関係していると考えられます。
石上神宮は、神話の時代から続く、厳格な神域であり、参拝者を選ぶ、という考え方が、「呼ばれないと行けない」という言葉を生み出したのかもしれません。
- 日本最古の神社の一つ: 石上神宮は、記紀神話にも登場する、日本最古の神社の一つです。その歴史の長さと、神話との繋がりが、特別な格式と、神秘的な雰囲気を作り出しています。
- 強力な神威: 石上神宮は、武の神様、そして健康長寿の神様として知られ、古くから朝廷や武士の崇敬を集めてきました。その強力な神威ゆえに、参拝にふさわしい人物、神様に呼ばれた人物だけが、訪れることができる、と考えられているのかもしれません。
- 禁足地(きんそくち): 石上神宮には、古くから禁足地とされる場所があり、一般の人は立ち入ることができません。神聖な場所を守るための禁足地の存在が、「呼ばれないと行けない」というイメージを強めているのかもしれません。
- 物部氏の総氏神: 石上神宮は、古代の有力氏族である物部氏の総氏神であり、物部氏との深いつながりがあります。
- 神様との相性: 全ての人に合う神社ばかりではなく、神様との相性もあると考える人がいます。
「呼ばれる」体験談の例:
- 何度も石上神宮に行こうと計画するが、その度に何らかの理由で、行くことができなくなる。
- 逆に、予定していなかったのに、急に石上神宮に行くことになる。
- 石上神宮に関する情報(夢、人からの話、シンクロニシティなど)が、頻繁に目や耳に入ってくるようになる。
- 石上神宮を訪れた後、人生が良い方向に進み始める、あるいは、心身の不調が改善される。
石上神宮 おすすめスポット:神話の時代から続く、神秘と歴史を感じる
石上神宮は、境内全体が、神話の時代から続く、神秘と歴史を感じさせる空間です。ここでは、特におすすめのスポットを厳選し、その魅力と、参拝のポイントをご紹介します。神聖な空気を感じ、心身を清め、明日への活力をいただきましょう。
- 拝殿:
- 特徴: 国宝に指定されている、鎌倉時代前期の建築。優美な曲線を描く屋根が特徴的です。
- 参拝のポイント: まずは、拝殿で心を込めて参拝しましょう。
- 禁足地:
- 特徴: 拝殿の後方、本殿がない場所に、禁足地があります。古くから神聖な場所として守られてきました。
- 参拝のポイント: 禁足地の中に入ることはできませんが、その存在を感じ、神聖な空気に触れることができます。
- 楼門:
- 特徴: 重要文化財。
- 境内を自由に歩く鶏:
神鶏として大切にされている鶏がいます。 - 七支刀(しちしとう):
- 特徴: 国宝に指定されている、古代の鉄剣。石上神宮に伝わる宝物です。(通常非公開)
- 歴史的価値: 七支刀は、古代の日本と朝鮮半島との交流を示す、貴重な資料としても知られています。
- 摂社 出雲建雄神社拝殿:
- **特徴:**こちらも国宝に指定されている建造物
参拝のポイント:
- 服装: 神様の前ですので、清潔感のある服装を心がけましょう。
- 静粛に: 境内では、静かに過ごしましょう。
石上神宮 近隣の観光地や名所:歴史と自然、そして美味しいグルメを満喫する
石上神宮周辺には、歴史的な建造物、美しい自然、そして、美味しいグルメを楽しめるスポットがたくさんあります。ここでは、石上神宮と合わせて訪れたい、おすすめの場所をご紹介します。奈良の歴史と文化、そして自然を満喫し、思い出に残る旅にしましょう。
- 天理市トレイルセンター: 古道「山の辺の道」の出発点。ハイキングコースの情報を入手できます。
- 山の辺の道: 石上神宮から奈良市まで続く、日本最古の道。自然豊かな道を歩き、古代のロマンを感じることができます。
- 長岳寺(ちょうがくじ): 石上神宮から徒歩圏内にある、美しい庭園で知られる古刹。
- 奈良公園: 鹿と触れ合える、広大な公園。東大寺や春日大社など、世界遺産の寺社仏閣も訪れることができます。
- 天理参考館 天理大学の附属博物館であり、世界の生活文化や考古美術に関する資料を展示。
石上神宮は、単なる観光地ではなく、日本の神話と歴史、そして文化が息づく、特別な場所です。「呼ばれないと行けない」という言葉は、石上神宮が持つ神秘性、そして、訪れる人々との間に生まれる、目に見えない繋がりを象徴しているのかもしれません。
ぜひ、あなた自身の心で、石上神宮のパワーを感じ、神話の世界を体感してください。
8. 大神神社(奈良県)
- 住所: 奈良県桜井市三輪
- 御祭神: 大物主大神(おおものぬしのおおかみ)
- 特徴:
- 日本最古の神社の一つであり、三輪山を御神体とする、本殿を持たない神社。
- 大物主大神は、国造りの神様、蛇神としても知られ、古くから信仰を集めている。
- 境内には、狭井神社、久延彦神社など、摂社・末社が多数ある。
- 注意点:
- 三輪山への入山は、狭井神社で許可を得る必要がある。
- 三輪山は神聖な場所なので、登山道以外には立ち入らないこと。
- 禁足地など、立ち入りが禁止されている場所もあるので注意
大神神社(奈良県):なぜ「呼ばれないと行けない」のか? 三輪山信仰、原初の神祀りの形
大神神社(おおみわじんじゃ)は、奈良県桜井市に鎮座し、日本最古の神社のひとつとされています。三輪山を御神体として祀り、本殿を持たない、原初の神祀りの形を今に伝えています。
古来より、国造りの神、生活全般の守護神として信仰を集め、近年ではパワースポットとしても人気です。
その神秘性と格式の高さから、「呼ばれないと行けない」という言葉を耳にすることもあるでしょう。
その理由や、参拝時のポイント、周辺情報まで、詳しくご紹介します。
なぜ「呼ばれないと行けない神社」と言われているのか?:三輪山への畏敬、神と人との距離感
大神神社が「呼ばれないと行けない」と言われる背景には、三輪山全体をご神体とする信仰形態、そして、そこから生まれる畏敬の念が深く関係していると考えられます。
大神神社は、自然そのものを神として崇める、古神道の姿を今に伝える、特別な場所。
そのため、参拝には、心の準備と、神聖な場所への敬意が必要とされ、それが「呼ばれる」「呼ばれない」という言葉に繋がっているのかもしれません。
- 三輪山信仰: 大神神社は、三輪山全体をご神体として祀っています。山そのものが神様であるため、畏敬の念を抱きやすく、誰でも気軽に訪れるべき場所ではない、という意識が生まれやすいと考えられます。
- 本殿がない: 大神神社には、本殿がありません。これは、三輪山そのものがご神体であるため、人工的な建物を必要としない、という考え方に基づいています。本殿がないことが、より一層、神聖な雰囲気を醸し出し、「呼ばれないと行けない」というイメージを強めているのかもしれません。
- 禁足地(きんそくち): 三輪山には、古くから禁足地とされる場所があり、一般の人は立ち入ることができません。神聖な場所を守るための禁足地の存在が、特別感を高めているのでしょう。
- 強力なパワースポット: 大神神社は、強力なパワースポットとして知られ、強いエネルギーを持つ場所とされています。そのため、心身の準備が整っていないと、そのエネルギーに圧倒されてしまう、体調を崩してしまう、などの体験をする人がいるのかもしれません。
- 神様との相性: 神社には相性があり、誰でも歓迎されるわけではないと考える人もいるようです。
「呼ばれる」体験談の例:
- 何度も大神神社に行こうと計画するが、その度に何らかの理由で、行くことができなくなる。
- 逆に、予定していなかったのに、急に大神神社に行くことになる。
- 大神神社に関する情報(夢、人からの話、シンクロニシティなど)が、頻繁に目や耳に入ってくるようになる。
- 大神神社を訪れたあと、人生が良い方向へ進み始める。
大神神社 おすすめスポット:原初の信仰に触れ、大地のエネルギーを感じる
大神神社は、境内全体が、神聖な空気に包まれています。ここでは、特におすすめのスポットを厳選し、その魅力と、参拝のポイントをご紹介します。三輪山の自然と一体となり、大地のエネルギーを感じ、心豊かな時間を過ごしましょう。
- 拝殿:
- 特徴: 三輪山をご神体として拝むための建物。現在の拝殿は、江戸時代に徳川家綱によって再建されたものです。
- 参拝のポイント: まずは、拝殿で心を込めて参拝しましょう。二拝二拍手一拝の作法で参拝。
- 三ツ鳥居(みつとりい):
- 特徴: 三つの鳥居を組み合わせた、独特の形をした鳥居。重要文化財に指定されています。
- 神聖な場所: 拝殿を通して見ることができ、直接の参拝(立ち入り)はできません。
- 巳の神杉(みのかみすぎ):
- 特徴: 大物主大神(おおものぬしのおおかみ)の化身である蛇(巳)が棲むとされる杉の木。
- ご利益: 金運アップ、病気平癒などのご利益があるとされています。
- 巳の好物の卵がお供えされています。
- 狭井神社(さいじんじゃ):
- 特徴: 三輪山の登拝口にある神社。病気平癒の神様として信仰されています。
- ご神水: 狭井神社の境内には、「薬井戸」と呼ばれる井戸があり、ご神水をいただくことができます。万病に効く霊水と言い伝えられています。
- 三輪山登拝: 三輪山に登拝するには、狭井神社で許可を得る必要があります(入山料が必要)。
- 諸注意: 入山受付時間、天候などを必ず事前に確認して計画を立てましょう。
- 久延彦神社(くえひこじんじゃ):
- 特徴: 知恵の神様である久延毘古命(くえびこのみこと)を祀る神社。学業成就や合格祈願にご利益があるとされています。
- 展望台からは大和平野が一望。
参拝のポイント:
- 服装: 神様の前ですので、清潔感のある服装を心がけましょう。
- 静粛に: 境内では、静かに過ごしましょう。
- 写真撮影: 境内での写真撮影は可能ですが、神様や社殿を直接撮影するのは失礼にあたる場合があるので、注意しましょう。
大神神社 近隣の観光地や名所:歴史と自然、そして美味しいグルメを満喫する
大神神社周辺には、歴史的な建造物、美しい自然、そして、美味しいグルメを楽しめるスポットがたくさんあります。ここでは、大神神社と合わせて訪れたい、おすすめの場所をご紹介します。奈良の歴史と文化、そして自然を満喫し、思い出に残る旅にしましょう。
- 山の辺の道: 石上神宮から大神神社、そして奈良市へと続く、日本最古の道。自然豊かな道を歩き、古代のロマンを感じることができます。
- 箸墓古墳(はしはかこふん): 卑弥呼の墓ではないかという説もある、巨大な前方後円墳。
- 談山神社(たんざんじんじゃ): 紅葉の名所として知られる、美しい神社。
- 長谷寺(はせでら): 「花の御寺」として知られ、四季折々の花々が美しい寺院。
- 三輪そうめん: 三輪はそうめん発祥の地とされています。ぜひ、本場の三輪そうめんを味わってみてください。
- 今西酒造(みむろ杉) : 大神神社の御神酒「みむろ杉」醸造元。試飲も楽しめます。
大神神社は、単なる観光地ではなく、日本の神道、歴史、そして文化が息づく、特別な場所です。「呼ばれないと行けない」という言葉は、大神神社が持つ神秘性、そして、訪れる人々との間に生まれる、目に見えない繋がりを象徴しているのかもしれません。
ぜひ、あなた自身の心で、大神神社のパワーを感じ、三輪山の大自然に抱かれて、心身ともにリフレッシュしてください。
9. 宗像大社(福岡県)
- 住所: 福岡県宗像市
- 御祭神:
- 沖津宮:田心姫神(たごりひめのかみ)
- 中津宮:湍津姫神(たぎつひめのかみ)
- 辺津宮:市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)
- 特徴:
- 沖ノ島、大島、本土の三ヶ所にそれぞれ宮があり、三女神を祀っている。
- 古くから航海の安全を守る神様として信仰を集めてきた。
- 沖ノ島は、女人禁制の島として知られ、現在も厳格な নিয়মが守られている。
- 注意点:
- 沖ノ島へは、一般の人は立ち入ることができない。
- 大島へは、フェリーで渡ることができる。
宗像大社(福岡県):なぜ「呼ばれないと行けない」のか? 海の正倉院、世界遺産の神秘
宗像大社は、福岡県宗像市に鎮座し、沖ノ島、大島、本土(田島)の三宮にそれぞれ女神を祀る、日本でも有数の古社です。
古くから航海の安全、交通安全の神様として信仰を集め、「神宿る島」沖ノ島と関連遺産群は、ユネスコの世界文化遺産にも登録されています。
広大な境内、豊かな自然、そして、悠久の歴史…。
この特別な神社にも、「呼ばれないと行けない」という言い伝えがあります。その理由を探り、魅力に迫ります。
なぜ「呼ばれないと行けない神社」と言われているのか?:厳格な信仰、女人禁制、そして神の意志
宗像大社が「呼ばれないと行けない」と言われる背景には、この神社が持つ特殊な信仰形態、地理的な特徴、そして、そこに祀られている神々の力が関係していると考えられます。
宗像大社は、古来より海上交通の要衝を守る神社であり、その信仰は厳格で、特別なものでした。特に沖ノ島は、女人禁制であり、一般の人は立ち入ることができない、神聖な島とされてきました。これらの要素が、「呼ばれないと行けない」というイメージを強めているのかもしれません。
- 厳格な信仰: 宗像大社は、古くから航海の安全を守る神様として信仰されてきました。そのため、参拝には、厳しい নিয়মや作法があり、誰でも気軽に訪れるべき場所ではない、という意識が生まれたのかもしれません。
- 沖ノ島の存在: 宗像大社の沖津宮がある沖ノ島は、女人禁制の島であり、一般の人は立ち入ることができません。島全体がご神体であり、古代からの祭祀遺跡が数多く残されています。「神宿る島」とも呼ばれ、その神秘性が、「呼ばれないと行けない」という言葉に繋がっているのでしょう。
- 三女神の存在: 宗像大社に祀られているのは、宗像三女神と呼ばれる三柱の女神です。女神は、時に気まぐれで、人を選ぶ、というイメージがあり、それが「呼ばれないと行けない」という言い伝えに影響を与えているのかもしれません。
- 特別なご縁: 神社には相性があり、誰でも歓迎されるわけではないという考えを持つ人も。
「呼ばれる」体験談の例:
- 何度も宗像大社に行こうと計画するが、その度に何らかの理由で、行くことができなくなる。
- 逆に、予定していなかったのに、急に宗像大社に行くことになる。
- 宗像大社に関する情報(夢、人からの話、シンクロニシティなど)が、頻繁に目や耳に入ってくるようになる。
- 宗像大社を訪れた後、人生が良い方向へ進み出す。
宗像大社 おすすめスポット:三宮を巡り、悠久の歴史と自然に触れる
宗像大社は、沖ノ島にある沖津宮(おきつみや)、大島にある中津宮(なかつみや)、本土(田島)にある辺津宮(へつみや)の三宮から構成されています。それぞれの宮には、異なる女神が祀られており、異なる魅力があります。ここでは、特におすすめのスポットを厳選し、その魅力と、参拝のポイントをご紹介します。
- 辺津宮(へつみや):
- 御祭神: 市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)…宗像三女神の一柱
- 特徴: 宗像大社の本宮であり、最も多くの参拝者が訪れる場所。
- おすすめスポット:
- 本殿・拝殿: 厳かな雰囲気の本殿と拝殿。心静かに参拝しましょう。
- 高宮祭場: 宗像大社で最も古い祭祀場とされる場所。古代の祭祀の様子を偲ぶことができます。
- 第二宮・第三宮: 沖津宮、中津宮の御祭神をそれぞれ祀る社。沖ノ島、大島に行けない場合は、こちらで参拝を。
- 神宝館: 国宝である沖ノ島の出土品などを展示している施設。
- 中津宮(なかつみや):
- 御祭神: 湍津姫神(たぎつひめのかみ)…宗像三女神の一柱
- 特徴: 大島に鎮座し、自然豊かな場所にあります。
- おすすめスポット:
- 本殿・拝殿: 海を見下ろす高台にあり、景色が良いです。
- 天の川: 境内を流れる小川。七夕伝説発祥の地とも言われています。
- 沖津宮(おきつみや):
- 御祭神: 田心姫神(たごりひめのかみ)…宗像三女神の一柱
- 特徴: 沖ノ島に鎮座し、一般の人は立ち入ることができません。
- 遥拝所: 大島の北端には、沖津宮を遥拝できる場所(沖津宮遥拝所)が設けられています。
参拝のポイント:
- 三宮を巡る: 時間と体力に余裕があれば、ぜひ三宮全てを巡ってみましょう。それぞれの宮の、異なる雰囲気を味わうことができます。
- 船を利用する: 中津宮(大島)へは、神湊(こうのみなと)港からフェリーまたは旅客船で渡ります。
- 沖ノ島: 4世紀後半から約500年間に渡り、航海の安全と国家の安泰を祈る大規模な祭祀が行われ、
8万点にも及ぶ様々な品が出土。そのことから「海の正倉院」とも称される。 - 服装について: 神社では節度ある服装での参拝を心がけましょう。
宗像大社 近隣の観光地や名所:歴史と自然、そして海の幸を満喫する
宗像大社周辺には、歴史的な建造物、美しい自然、そして、新鮮な海の幸を楽しめるスポットがたくさんあります。ここでは、宗像大社と合わせて訪れたい、おすすめの場所をご紹介します。宗像の魅力を、余すところなく満喫しましょう。
- 道の駅むなかた: 地元の特産品やお土産が揃う、人気の道の駅。新鮮な魚介類を使った海鮮丼などがおすすめです。
- 鎮国寺(ちんこくじ): 空海(弘法大師)が創建したと伝えられる、真言宗の古刹。
- 宮地嶽神社(みやじだけじんじゃ): 光の道で有名な神社。巨大なしめ縄、大太鼓、大鈴は、日本一の大きさを誇ります。
- 新原・奴山古墳群(しんばる・ぬやまこふんぐん): 宗像大社の神領内に築かれた、古墳群。世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群の構成資産の一つです。
- さつき松原: 玄界灘に面した海岸線に約5kmにわたり続く松原。
- 鐘崎漁港: 新鮮な魚介類が水揚げされる漁港。近くには、海鮮料理を楽しめるお店がたくさんあります。
宗像大社は、単なる観光地ではなく、日本の歴史と文化、そして信仰が息づく、特別な場所です。「呼ばれないと行けない」という言葉は、宗像大社が持つ神秘性、そして、訪れる人々との間に生まれる、目に見えない繋がりを象徴しているのかもしれません。
ぜひ、あなた自身の心で、宗像大社のパワーを感じ、海と空と神々が織りなす、壮大な世界を体感してください。
10. 富士山本宮浅間大社(静岡県)
- 住所: 静岡県富士宮市宮町
- 御祭神:
- 木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと)
- 特徴:
*全国に1300社以上ある浅間神社の総本宮。- 富士山を御神体とする、古くからの山岳信仰の拠点。
- 美しい湧水が湧き出る「湧玉池」は、国の特別天然記念物に指定されている。
- 注意点:
*富士山の神様は女性なので、嫉妬を避けるため、カップルでの参拝は避けたほうがいいという言い伝えも。- 富士山への登山道は、開山期間が限られているため、事前に確認すること。
以上、「呼ばれないと行けない」と噂される神社10選をご紹介しました。
これらの神社は、いずれも長い歴史を持ち、多くの人々に信仰されてきた、特別な場所です。
もし、あなたがこれらの神社に呼ばれたと感じたら、ぜひその導きに従って、参拝してみてください。
きっと、素晴らしい体験が、あなたを待っているはずです。
富士山本宮浅間大社(静岡県):なぜ「呼ばれないと行けない」のか? 富士の神霊と繋がる、特別な場所
富士山本宮浅間大社は、静岡県富士宮市に鎮座し、富士山を御神体とする、全国に1300社以上ある浅間神社の総本宮です。ユネスコの世界文化遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産の一つでもあります。古くから富士山信仰の中心地として、多くの人々の信仰を集めてきましたが、この浅間大社にも「呼ばれないと行けない」という言葉を耳にすることがあります。それは一体なぜなのでしょうか?
なぜ「呼ばれないと行けない神社」と言われているのか?:富士山の神威、厳格な信仰、そして試される心
富士山本宮浅間大社が「呼ばれないと行けない」と言われる背景には、富士山そのものを神と崇める信仰、そして、富士山の持つ圧倒的な自然の力、さらには、神社の格式の高さが関係していると考えられます。富士山は、古来より神聖な山として、畏敬の念を集めてきました。その神威は強大であり、参拝には、心の準備と、神様への敬意が必要とされ、それが「呼ばれる」「呼ばれない」という言葉に繋がっているのかもしれません。
- 富士山を御神体とする信仰: 富士山本宮浅間大社は、富士山そのものを御神体として祀っています。そのため、神社を参拝することは、富士山を参拝することと同じ意味を持ちます。富士山の持つ圧倒的な自然の力、そして、神聖なエネルギーは、時に人を圧倒し、選別する、という考え方が生まれたのかもしれません。
- 厳格な信仰の歴史: 富士山本宮浅間大社は、古くから山岳信仰の拠点であり、富士山登拝の出発点でもありました。富士山への登拝は、厳しい修行であり、神聖な行為。その厳格な信仰の歴史が、「呼ばれないと行けない」というイメージを強めているのかもしれません。
- 強力なパワースポット: 富士山本宮浅間大社は、強力なパワースポットとして知られています。そのため、心身の準備が整っていないと、そのエネルギーに圧倒されてしまう、体調を崩してしまう、などの体験をする人がいるのかもしれません。
- 浅間大神(木花之佐久夜毘売命)の気高さ: 富士山本宮浅間大社の御祭神である木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと)は、美しく、気高い女神として知られています。その気高さゆえに、参拝者を選ぶ、というイメージがあるのかもしれません。
- 神様との相性: 相性の良くない神社にいくと、歓迎されずトラブルが起きることがあると考える人もいるようです。
「呼ばれる」体験談の例:
- 何度も富士山本宮浅間大社に行こうと計画するが、その度に何らかの理由で、行くことができなくなる。
- 逆に、予定していなかったのに、急に富士山本宮浅間大社に行くことになる。
- 富士山本宮浅間大社に関する情報(夢、人からの話、シンクロニシティなど)が、頻繁に目や耳に入ってくるようになる。
- 富士山本宮浅間大社を訪れた後、人生が良い方向に進み始める。
富士山本宮浅間大社 おすすめスポット:富士の恵みを感じ、神聖な空気に包まれる
富士山本宮浅間大社は、広大な境内の中に、数多くの見どころがあります。ここでは、特におすすめのスポットを厳選し、その魅力と、参拝のポイントをご紹介します。富士山の雄大な姿を仰ぎ見、神聖な空気に包まれ、心豊かな時間を過ごしましょう。
- 本殿:
- 特徴: 浅間造(せんげんづくり)と呼ばれる、二層の楼閣造りの珍しい建築様式。国の重要文化財に指定されています。
- 参拝のポイント: まずは、本殿で心を込めて参拝しましょう。
- 拝殿:
- 特徴: 参拝者が祈りを捧げる場所。
- 参拝のポイント: 鈴を鳴らし、二礼二拍手一礼の作法で参拝しましょう。
- 湧玉池(わくたまいけ):
- 特徴: 富士山の雪解け水が湧き出る、清らかな池。国の特別天然記念物に指定されています。
- ご利益: 湧玉池の水は、古くから霊水として信仰され、心身を清める力があるとされています。
- 水屋で水 বিশ্ববিদ্যালয়ের
- 桜の馬場(流鏑馬像):
- 流鏑馬神事が行われる。
- 富士山頂: 境内にはないですが、浅間大社の一部。
- 特徴: 時間と体力がある方は、ぜひ富士登山にも挑戦してみてください。山頂からのご来光は、まさに絶景です。
参拝のポイント:
- 服装: 神様の前ですので、清潔感のある服装を心がけましょう。
- 湧玉池の水: 湧玉池の水を飲むことはできませんが、手を清めることはできます。
富士山本宮浅間大社 近隣の観光地や名所:富士山の恵みを満喫する旅
富士山本宮浅間大社周辺には、富士山の自然、歴史、文化、そしてグルメを楽しめるスポットがたくさんあります。ここでは、富士山本宮浅間大社と合わせて訪れたい、おすすめの場所をご紹介します。富士山の恵みを満喫し、思い出に残る旅にしましょう。
- 白糸の滝: 富士山の雪解け水が、数百条の細い滝となって流れ落ちる、美しい滝。国の名勝及び天然記念物に指定されています。
- 音止の滝: 白糸の滝の近くにある、迫力満点の滝。
- 富士山世界遺産センター: 富士山の自然、歴史、文化に関する展示施設。
- 朝霧高原: 富士山を望む、広大な高原。パラグライダーやキャンプなど、様々なアクティビティを楽しめます。
- まかいの牧場: 動物と触れ合える、人気の観光牧場。
- 田貫湖 キャンプ場もあり、自然を大満喫できるスポット
- 富士宮やきそば: 富士宮市のご当地グルメ。コシのある麺と、肉かす、イワシの削り粉が特徴。
富士山本宮浅間大社は、単なる観光地ではなく、日本の象徴である富士山を祀る、特別な場所です。「呼ばれないと行けない」という言葉は、富士山本宮浅間大社が持つ神聖さ、そして、訪れる人々との間に生まれる、目に見えない繋がりを象徴しているのかもしれません。
ぜひ、あなた自身の心で、富士山本宮浅間大社のパワーを感じ、富士山の雄大な自然に抱かれて、心身ともにリフレッシュしてください。
「呼ばれないと行けない神社」まとめ:神域からの招待状、その真意とは
「呼ばれないと行けない神社」とは、特定の神社とご縁が深い人、または参拝すべきタイミングが来た人だけが、何らかの形で招かれるように訪れることができる、という神秘的な考え方に基づくものです。
要点まとめ:
- 「呼ばれる」とは?:
- 夢で見る、偶然の出会い、人からの勧め、シンクロニシティ、直感など、様々な形で現れる。
- 特定の神社との、目に見えない繋がり、あるいは、参拝すべきタイミングを知らせるサイン。
- 科学的な根拠はないが、多くの人が不思議な体験をしていることも事実。
- なぜ「呼ばれないと行けない」と言われるのか?:
- 強力な神域の結界: 不浄なものや、参拝にふさわしくない人を阻むとされる。
- 厳しい修行の地: かつての修行場であり、容易には辿り着けない場所だった歴史的背景。
- 特別な神様: 人を選ぶ、強力な力を持つ神様が祀られている。
- 神様からの試練: 参拝までの道のりで、様々な試練を与えることがある。
- 相性: 全ての神社がその人に合うとは限らず、相性の良い、選ばれた人のみが招かれるという考え方
- 「呼ばれない」場合の体験談:
- 何度計画しても、その度に何らかの理由で、行くことができなくなる。
- 行こうとすると体調を崩したり、急用ができたりする
- 「呼ばれる」場合の体験談:
- 予定していなかったのに、なぜか急に行くことになる。
- その神社の情報を頻繁に見聞きするようになる。
- 「呼ばれないと行けない」とされる神社の特徴:
- 古くからの歴史を持つ、格式の高い神社が多い。
- 強力なパワースポットとして知られていることが多い。
- 自然豊かな場所、あるいは、厳しい環境の中に鎮座していることが多い。
- 特定の神様(龍神、天狗、女神など)を祀っていることが多い。
- 「呼ばれないと行けない神社」に参拝する際の心構え:
- 「呼ばれた」と感じたら、素直にその導きに従う。
- 神様への感謝の気持ちを忘れず、敬意を持って参拝する。
- 心身を清め、清らかな気持ちで参拝する。
- 個人的なお願い事だけでなく、日頃の感謝を伝えることを意識する。
- 何か特別な体験をしても、むやみに人に話したり、自慢したりしない。
- 大切なこと:
- 「呼ばれないと行けない」という言葉に、とらわれすぎないこと。
- 行きたい神社があれば、まずは自分の心に正直に、参拝してみること。
- 神社とのご縁は、自分自身の心の状態によって、変化することもある。
「呼ばれないと行けない神社」という考え方は、神社との神秘的な繋がりを感じさせてくれる、興味深いものです。
しかし、最も大切なのは、あなた自身の心です。
「呼ばれた」と感じなくても、あなたが参拝したいと思う神社があれば、ぜひ、その気持ちを大切に、足を運んでみてください。
神様は、きっとあなたの純粋な気持ちに応えてくださるはずです。



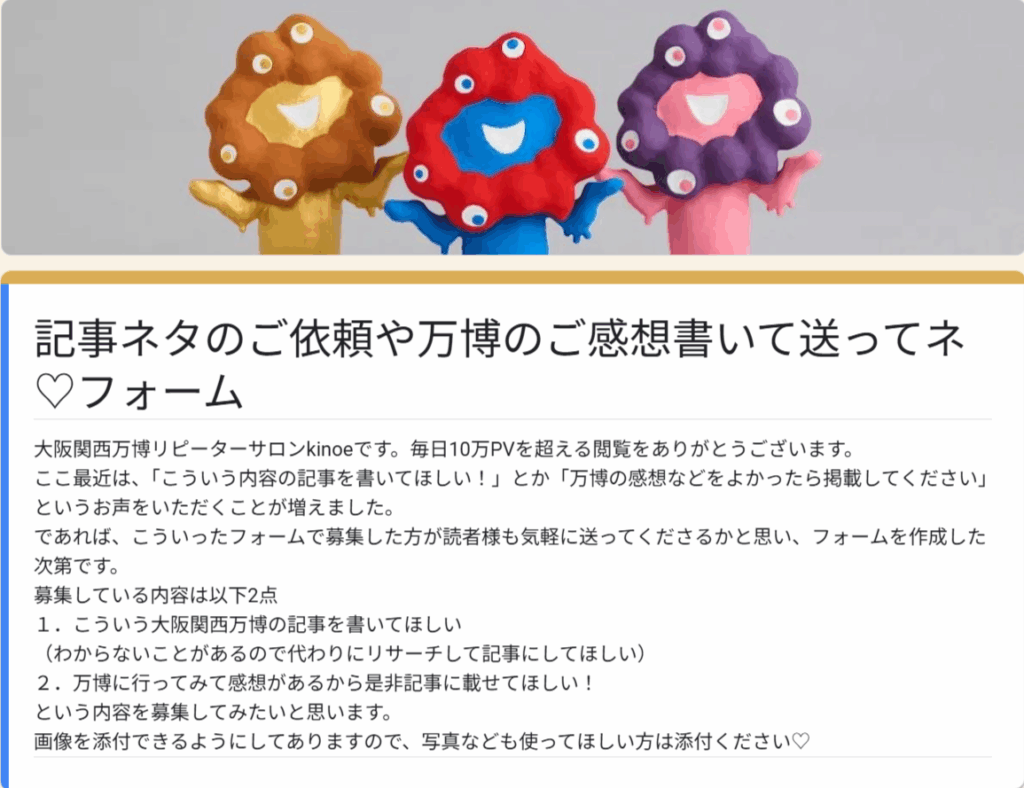



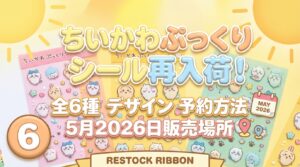





コメント